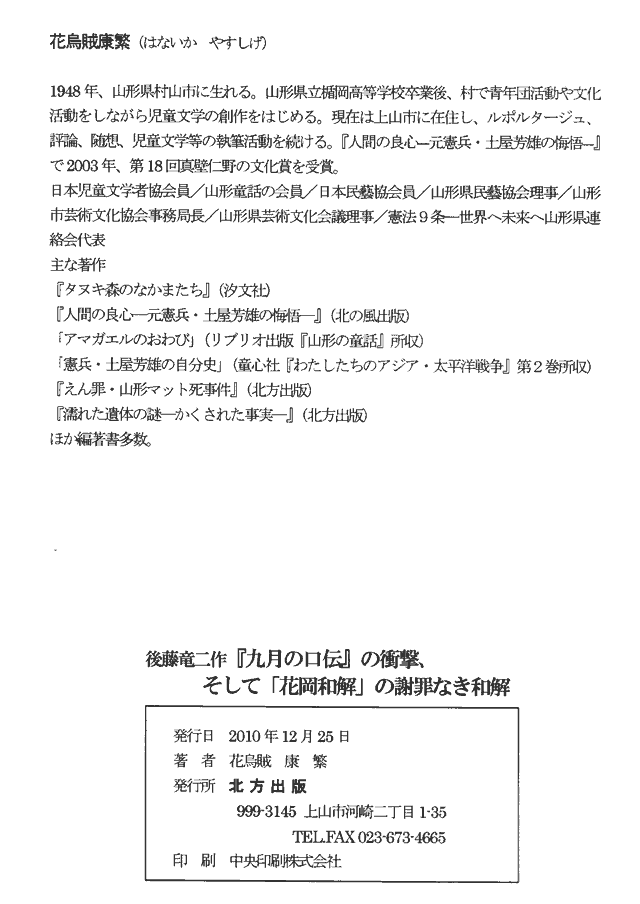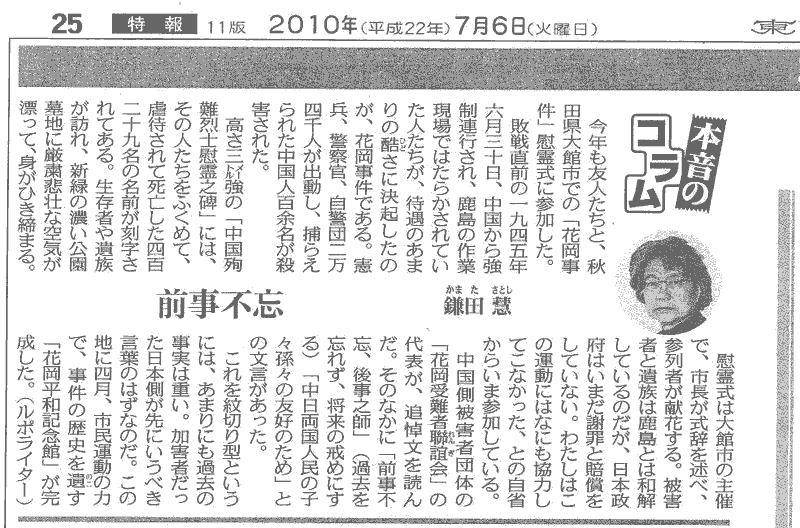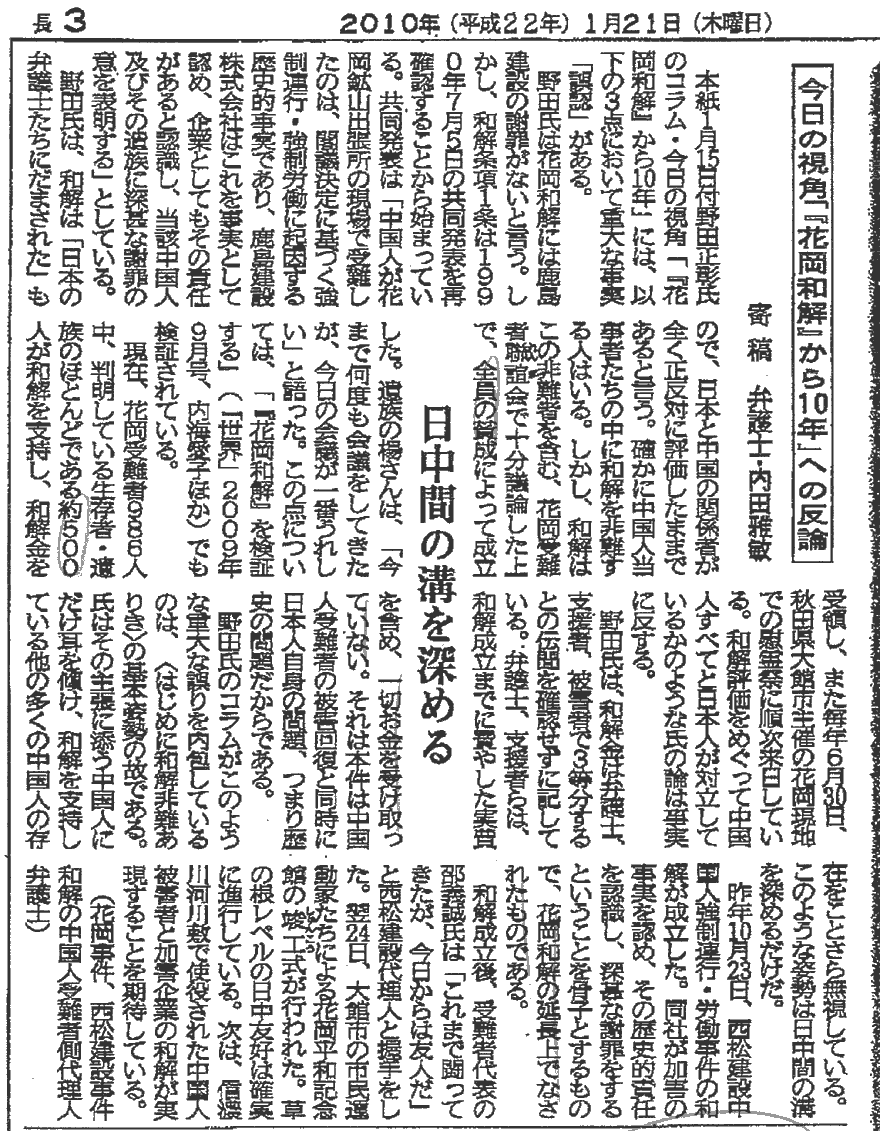中華人民共和国 王毅外交部長 殿
中華人民共和国駐日本国大使館 程永華大使 殿
戦時日本の強制連行・強制労働に関する中国法廷での裁判審理についての意見書
2015年2月11日、戦時中に行われた強制連行・強制労働をめぐって、中国人被害者および遺族と三菱マテリアル(旧三菱鉱業)との間で行われていた和解交渉が決裂したことが、日中双方のメディアで伝えられた。
和解交渉のなかで中国人被害者・遺族は、 加害の事実と責任の所在が明確にされたうえで、当該企業の法的責任に基づく賠償金が拠出されることを求めていた。ところが、三菱側は「雇用主としての歴史的責任」を認めるという立場にこだわり、強制連行の要請や連行後の虐待・虐殺の主体者であったという事実を認めず、法的責任の回避に終始したという。これは、日本の裁判所における法廷審理の際に示された同社の立場表明と何ら変わっていない。
90年代後半から2000年代にかけて 日本の裁判所に提訴された強制連行・強制労働訴訟では、最終的に時効や国家無答責、「日中共同声明による解決済み」論で強制連行被害者が敗訴した。判決では被害の事実認定が行われるケースもあったが、賠償は行われていない。
その後、被害者・遺族らが中国の裁判所に提訴するようになったこと、昨年2月には三菱マテリアルに対する訴状が初めて受理されているといった事実から、被害者やその遺族はもちろん中国の裁判所も、日本の司法が示した強制連行・強制労働問題の判決や和解が問題の「解決」になっておらず、不当なものだと受け止めていることを物語っている。
今回決裂した和解交渉では、三菱側は「雇用主」として「歴史的責任」を持つに過ぎないという自己認識を示した。強制連行や奴隷労働、虐待・虐殺が行われていた事実を踏まえれば、一般的な「雇用関係」にとどまるものではないことは明白であり、戦争犯罪に該当する重大な人権侵害と捉えるべきである。加害の事実やその責任を明確にするという被害者の第一要求がこのように曖昧化されているのであれば、交渉が決裂しない方が不思議である。三菱側のこうした態度は、事実認定だけは行った日本の司法判断からも大幅に後退している。
このような状況の中で金銭の拠出を優先して「和解」を成立させてしまっては、現在の日中間の最大の問題である「歴史問題」の解決にも繋がらないことはいうまでもない。被害者自身の体験や戦後に家族や地域社会が受けた影響、民衆の戦争記憶は、何よりもまず日本の加害主体が罪を認めて責任を引き受けることなしに、「戦後」を迎えることができないからである。「政治解決」や「日中友好」もまた、歴史事実とその責任を曖昧にせず、明確化することではじめて成り立つものである。
このことを雄弁に裏付ける事例が、強制連行における「和解」の先行例としての「花岡和解」「西松和解」である。前者では、故・耿諄原告団長をはじめ複数の原告が事実と責任を曖昧にした「和解」の受け入れを拒んだ。後者でも、同和解を「花岡和解」型の曖昧解決だと主張した原告が、和解当事者から外されてしまい、全面的な解決とは程遠いものとなっている。今回決裂した三菱との和解交渉においても、事実認定や責任の所在、謝罪のあり方が曖昧なまま基金が拠出されるのでは、花岡・西松型の「和解」の域を出ておらず、和解金の額面以外に「前進」があったとはいえない。花岡「和解」や西松「和解」が成立した際には、「画期的和解」「今後の包括的な解決へのステップ」といった形で評価する声が支配的だったが、その後、最高裁ではすべて敗訴に終わり、「政治解決」も実現しておらず、何ら「次のステップ」に進んだ事実はない。今回、被害者・遺族らが交渉を打ち切ったのも、事実認定や責任のあり方でまったく前進がなかったことを示している。
逆にいえば、理路は単純であり、事実認定や法的責任を明確にした「和解」が成立すれば、強制連行・強制労働をめぐる「歴史問題」は解決へと大いに近づき、いつまでもくすぶり続けることはないだろう。われわれは、戦後70年という節目にあたって、当事者である当該企業および日本政府が加害の事実とその責任を直視することで、懸案である歴史問題の根本的解決を図ることを強く求める。
その意味で、敗戦後のBC級戦犯横浜裁判において、花岡事件での鹿島組職員らによる捕虜虐待・虐殺という戦争犯罪に対する法的責任が確定し、死刑等の判決が出ていたにもかかわらず、鹿島花岡訴訟において事実や責任を曖昧にした「和解」を成立させてしまったことは、戦犯裁判の結果からも大きく後退したとあらためて指摘しておく必要がある。
花岡「和解」成立後、産経新聞もまた一定の評価を下していた。しかし、それは「今回の和解が戦後賠償や戦後補償問題の枠組みを変えることはあり得ない」(2000年12月1日付) という判断の下でなされた評価であることに注意を喚起したい。事実認定も行わず、法的責任も認めず、賠償金も払わないにもかかわらず、「友好」「和解」が成り立ったことを、彼らは歓迎していたのである。事実、花岡「和解」成立後の強制連行・強制労働訴訟の法廷の場で、裁判所はしばしば「花岡型」の<法的責任抜きの「和解」>を提案してきた。戦後賠償でも戦後補償でもない「和解」の余地が生まれたことは誰を喜ばせたのかは明白である。
花岡「和解」後のこうした経緯を振り返れば、事実認定も法的責任も抜きにした「和解」を成立させることは、日本社会において戦争責任問題や戦争被害者の戦後補償を追及してきた市民や学者、法律家などの懸命な努力に対して「梯子を外す」ことにしかならず、日本社会の右傾化を棹さしてしまうのみである。実際に近年、日本の中国研究者たちの間で、中国の被害者・遺族の当然の要求を支持する声がきわめて希薄になっている。
こうした観点から、われわれは、 事実や責任を曖昧化しながら金銭の拠出を進めようとする和解案を問題の「解決」と見なさず、間もなく始まるとされる中国法廷での審理に基づき、事実の解明や責任の明確化を求めることを選んだ被害者・遺族および康健弁護士らの判断を強く支持する。2012年5月には、韓国の最高裁判所が戦時徴用被害について新日鉄住金に対し個人賠償を命じており、中国の裁判所においても同様の法的措置がとられることが期待されるところである。
中華人民共和国外交部および中華人民共和国駐日本国大使館にあっても、表面的な「中日友好」に配慮せず、中国民衆の被害および被害感情を解決する根本的な次元から「歴史問題」に向き合い、被害者や遺族が受け入れられる真の「解決」のために一層の努力を傾注されることを強く願うものである。
なお、ドイツの戦後処理は中国でも評価されているが、それは周辺国が被害国としての責務を果たしたがゆえの結果でもある。アジアの被害国が日本の加害責任を徹底して追及してこなかったことも、現在の状況を生み出した一因である。原則部分でさえ譲歩していては、中国は「法治国家」ではなく「人治国家」であるというイメージを増幅させるばかりである。被害者の「尊厳」を犠牲にするような一方的な譲歩で得られる「友好」が一時的なものに過ぎないことは、ここ20~30年の日中間の歴史が雄弁に物語っていることを今一度想起したい。
2015年2月28日
「私の戦後処理を問う」会 代表 山邉悠喜子
花烏賊康繁20101225花烏賊康繁20101225後藤竜二作『九月の口伝』の衝撃、そして「花岡和解」の謝罪なき和解 pdf
花烏賊康繁
『九月の口伝』の鮮烈さ
今年の七月三日、とつぜん、後藤竜二さんが逝った。六十七歳。たくさんの作品を残したといっても、あまりにも早すぎる。くやしくて、幾日たっても気持ちの整理がつかず、十一月二十二日、早稲田大学構内にあるリーガロイヤルホテルで行われた全国児童文学同人誌連絡会主催、「後藤竜二さんを偲ぶ会」に出かけた。
会場の中央に、純白の花につつまれて笑っている後藤竜二さんがいる。子どもたち、そして、多くの書き手をはげましつづけた後藤さんだった。
古田足日さんはじめ、小松崎進さん、那須正幹さん、広瀬恒子さん、最上一平さんなど、たくさんの方がたのお別れの言葉をききながら私は、後藤さんとの思い出をたどっていた。
たしか一九七六年だったと思う。「これ、読んでみろ」と、高橋徳義さんから「トマトとパチンコ」という短編を示された。作者は後藤竜二。『天使で大地はいっぱいだ』『大地の冬のなかまたち』(共に講談社)などですでに名をなしている作家だった。
その場で私が読み終えると、「こういう話ならお前も書けるんでないか」と徳義さんがいった。どんな風の吹きまわしだったのか、私はつい「うん」とこたえてしまった。それが児童文学の世界に足を踏み入れるきっかけになろうとは、思いもよらずに……。
「うん」とはいったものの、その場しのぎに答えただけで、私にはまったく書く気がなかった。が、顔を会わせるたびに「書いたかハ」と徳義さんから催促されるので、しかたなくなぐり書きで「タマゴをうむオンドリなんているか」と題する作品を書いた。これが児童文学といえるのかどうかもわからない。私の中では、徳義さんに読ませればそれで終わり、と思っていた。
ところが、私の知らぬまに徳義さんはそれを「山形童話の会」の機関誌『もんぺの子』に掲載。さらにその作品が『日本児童文学』一九七八年七月号の特集2「同人誌の課題」の中で取りあげられ、後藤竜二さんの「おまつり村」と並ぶ評価を受けてしまった。後藤さんと近しくなったのはそれが縁だったが、考えてみれば、高橋徳義さんや植松要作さんほか、周りの人たちからむりやり屋根に押し上げられ、降りるハシゴをはずされてしまった感じがしないわけでもない。
いつのまにか「山形童話の会」員にもなり、須藤克三先生の自宅で行なわれた例会にも参加していた。作家になるつもりなど毛頭ない私は、創作はともかく、須藤先生がよくいう「人間の生き方としての文化」創造の活動をしようと心ひそかに決め、できるだけたくさんの児童文学作品を読むことに熱中した。山形の作家の作品はもちろん、古田足日さんや長崎源之助さんなどの作品、そして後藤竜二さんの作品はほとんど欠かさず読んだ。
後藤竜二さんの作品は『天使で大地はいっぱいだ』にはじまり、『白赤だすき小○の旗風』(講談社)『少年たち』(講談社)『十四歳― Fight』(岩崎書店)『野心あらためず』(講談社)……いずれも特筆しなければならない作品ばかりだが、中でも私は『九月の口伝』(汐文社)に衝撃を受けた。私の知るかぎり、朝鮮人や中国人の強制連行・強制労働について児童文学で描いたのは、『九月の口伝』だけのような気がする。
いま私は山形県酒田港の中国人強制連行・強制労働にかかわる訴訟を支援し、また秋田県花岡の中国人強制連行・強制労働にからむ「花岡事件」・「花岡和解」を問い直すホームページ「私の戦後処理を問う会」の勉強会にも参加しているが、戦時中、日本が国策として朝鮮人や中国人を大量に拉致(らち)し、強制労働につかせていた事実に関心を持つようになったのも『九月の口伝』を読んでからだった。
『九月の口伝』― 舞台は、敗戦直後の北海道美唄。後藤竜二さんの故郷であり、後藤さんの自伝ともいえる児童文学作品である。
第三章「紅玉」― 秋祭りが終わったころ、美唄炭鉱の小学校で教師をしている伯父(父の次兄)が、農業をしている後藤さんの家に訪ねてきた。伯父のいる《美唄の炭鉱には、五千人の朝鮮人と千人の中国人たちがいる。……みんな、日本軍の「労工狩り」によって、祖国から強制連行されてきた人たちだ》。その朝鮮人や中国人たちが、日本の敗戦を知って暴動を起こしたという噂がひろまっている。炭鉱の様子はどうなんだ、と父が伯父にたずねた。伯父はいう。
《暴動も、略奪も、故意のデマだ。……デマを利用して、きのうの早朝、四百人もの警官隊が中国人収容所をおそった。……アメリカ軍の捕虜たちは、サイレンとともに一人残らずゆうゆうと引きあげていったが、中国人と朝鮮人たちは、帰国の見通しどころか、その日の食べ物にさえ困っている。国や会社のエライさんたちは、逃げまわって出てこない。しかたがないから、美唄や夕張など空知地方の中国人たち七千人が、たがいに連絡を取りあい、食料の増配、衣料品の支給、自由外出の許可というあたりまえの要求をした。堂々とやった。まさしく民主主義の手本じゃないか。それなのに、国や会社は、そうした動きをつぶすために、全道から四百人もの武装警官を集めて、とつぜん中国人収容所の寝込みをおそうというようなことまでやったのだ。―なんにも変っていない。戦争が終わったなんていっても、なんにも変ってはいないんだ!》
そういったあと伯父は、「警察官又ハ婦女子等ニ対スル暴行及金品ノ略奪行為アリ事態急ヲ要シ自衛上必要ナル場合ハ射殺スベシ」と念仏のように唱える。それは占領軍が出した〈おふれ〉だった。
伯父が帰った翌日、後藤さんの家のりんご畑が二、三〇名の中国人に襲われる。この地域でりんごを作っているのは後藤さんの家だけ。集まった隣人たちは、「災難だと思って、目ェつぶってるしかなかべ」「危ないから近づくな」と父にいう。が、父は、他人事にいう隣人たちにあきれ、自分の作物は自分で守るしかないと、骨と皮ばかりに飢えた中国人の群れのもとへふらふらと歩みはじめる。
《畑に向かう父の目の前には、上海のコーリャン畑がひろがっていた。あそこでは、徴発といって、日本の兵隊たちが、なんでもかんでも、あたりまえのことのように、うばい取っていた。りんごどころではない。うさぎ、にわとり、ぶた、牛、馬― そして、男も、女も》
りんご畑の中で父は、中国人たちに取り囲まれた。父はリーダーらしい男に「先生(シェンション)、先生」と呼びかける。そして、「オネガイダ、コノリンゴ、トランデクレ、コノリンゴ、ウッテ、カゾク、ヤシナウ。タノム、トランデクレ」と、軍隊でおぼえた中国語でいった。
「明白(わかった)」― リーダーの男が「これまでだ」と仲間たちに合図すると、中国人たちはポケットやふところから取りだした紅玉を、父の前にひとつ、ひとつと積み上げて山になっていった。そのときの父の心情を、後藤竜二さんはつぎのように描く。
《― 持っていってくれ!それくらい、持っていってくれ! 体の底からせりあがってくるふるえを必死でこらえながら、こころの中でさけぶのだが、声にはならず、なみだばかりがあふれてきて、父はむせかえるような紅玉のあまずっぱいにおいの中にぼうと立ったまま、ぼろの群れのような人びとが黒土の高台を去っていくのを見送っていた。》
ややもすると私たちは、この朝鮮人や中国人に紅玉を好きなだけもぎとらせ、与えてやることが、人間としての「善意」と思いがちだ。それが「反省」や「謝罪」をあらわす行為と自賛しかねない。が、後藤さんは、そうした自賛の陰にひそんでいるのは、彼らをあわれみ、ほどこしを与えて満足する手前勝手な論理であることを撃つ。そんな「善意」は、上からの目線で彼らをなお差別し、彼らの尊厳を踏みにじって善しとする感情ではないか、と作品の世界で射る。
『九月の口伝』で後藤さんは、中国人への加害者として、「認罪」「反省」「謝罪」にいたる父の感情を描いた。そして、「反省」や「謝罪」は、ほどこしを与える善意にあるのではなく、罪を背負って自分がどう生きようとしているのかを相手に語り、互いの尊厳を理解しあって対等に生きるしかないことを、信じられる言葉で伝えている。私にはそれが鮮烈であり、衝撃だった。これこそが、山形の児童文学や児童文化運動が求めてきた「人間の生き方としての文化」ではないか……と。
尊厳― 後藤竜二さんはそれを「誇り」という言葉にした。そして、「誇り高く生きぬく」には「野心を改めず」「服従せず」、「信じられる言葉」で「対等な人間関係」をつくること、と作品の中で私たちに提示しつづけた。その後藤さんの心底にあったのはおそらく、戦争が終わったなんていっても、「なんにも変っていない。なんにも変ってはいないんだ!」と伯父に激白させた日本人の精神構造、文化に、現在もなお私たちがどっぷりつかっていることに対する憂いだったのではなかったろうか。
後藤竜二さんを彼岸から呼びもどし、たずねてみたい。
強制連行と花岡蜂起
アジア・太平洋戦争中、日本は、朝鮮人や中国人の強制連行・強制労働を国策としてすすめた。戦争に勝とうと、どんどん兵力をつぎこんで不足した国内の炭鉱や鉱山、港湾などの労働力を、朝鮮人や中国人でおぎなおうとしたのだ。一九四四年の「国民動員計画」には朝鮮人二九万人、中国人三万人という目標がかかげられている。
中国人を現地で集める役割をになったのは日本軍だった。日本軍は、「労工狩り」または「ウサギ狩り」と称して中国の村むらを襲い、働けそうな男という男を手あたりしだい拉致(らち)した。そうやって日本に連れてこられた中国人は、外務省報告書の記載では三万八千九二九人にのぼる(野添憲治氏らの調査では、もっと多いと指摘されている)。この人たちは国内三五企業の一三五事業所にふり分けられ、いずれの事業所でも粗末な衣服と食事を与えられ、監視されながら奴隷労働を強いられた。
現秋田県大館市にあった花岡鉱山は、銅や鉛を産出する鉱山だったが、軍需工場に指定されてからの乱掘により、一九四五年に七ツ館鉱で落盤事故が発生した。その事故のあと、七ツ館鉱の上を流れる花岡川や大森川の改修工事を請負ったのが鹿島組(現鹿島建設)花岡出張所。そして、炭鉱労働を目的に強制連行された九八六人が急きょ、河川改修工事の作業人夫にふり分けられた。
中国人は第一陣から第三陣にわけて連行されている。第一陣の三〇〇人が貨物船「信濃丸」で日本に運ばれたのは一九四四年七月二十八日。三〇〇人の中国人は船のなかで軍隊式に三中隊に編成された。中国人を抑圧するのに中国人を使おうとの魂胆からである。各中隊をたばねる大隊長に指名されたのは耿諄(コウ・ジュン)氏だった(以下、すべて敬称略)。
第一陣が花岡に着いたのは八月。彼らは鹿島補導員や警察が監視する「中山寮」という飯場に収容され、そこから約四キロもはなれた花岡川の改修工事現場で、一日十二時間以上も酷使された。はじめは小麦粉の食事だったが、すぐにトチの実の粉だけになる。ひもじさをこらえての重労働。中国人たちは、たちまちやせおとろえ、極度の栄養失調におちいった。
ひもじさのあまり道ばたに生えた草を食べていると、監視の補導員がスコップでなぐりかかり、殺した。厳寒の川底での作業から凍傷になり、痛さで動けなくなる人もいる。ついに、立ったまま死に、ふうわりと雪の上に倒れる人が出はじめた。わずか一年のあいだに、第一陣三〇〇人のうち約一〇〇人がそうやって死亡、いや、殺された。第二陣、第三陣の中国人たちが着いても鹿島組の虐待は変わらず、むしろ激しさを増している。
このままではみな殺しだ。どうせ殺されるなら、尊厳を守って死のう ― 一九四五年六月三十日、耿諄大隊長を中心に中国人たちは蜂起。補導員四人ほかを殺害して獅子ケ森山へ逃げこんだ。すぐに警察や地元民による自警団の山狩りがはじまった。
生きてつかまった耿諄はじめ中国人たちは、木造の「共楽館」という劇場前の広場につながれ、警官の拷問、虐待にさらされる。蜂起からたった三日間で、さらに一〇〇人以上の中国人が殺された。ちなみに、鹿島組花岡出張所に強制連行された中国人九八六人のうち、四二パーセントにあたる四一九人が帰国まで死亡している。
「公開書簡」から損害賠償請求の提訴
生きて中国に帰った耿諄は一九八七年、宇都宮徳馬や田英夫、土井たか子らの招へいで来日し、十日間滞在した。そのとき、鹿島建設が「一切の責任はない、中国労工は募集によって来た契約労働者である、賃金は毎月支給した、遺族に救済金も出している……」とあまりにも事実とちがうことを主張していることを知り、「討回歴史公道」(歴史の公道をとりもどそう)と決意する。
そして二年後の一九八九年、かつて虜囚だった人びとが集まり、耿諄を会長として、鹿島建設に対し「公開書簡」を出した。
- 鹿島が心から謝罪すること。
- 鹿島が大館と北京に「花岡殉難烈士記念館」を設立し、後世の教育施設とすること。
- 受難者に対するしかるべき賠償をすること。
「公開書簡」には以上の三要求が記された。この三要求を基に一九九〇年一月から、新美隆弁護士、内田雅敏弁護士、「中国人強制連行を考える会」の田中宏教授、内海愛子、在日華僑の林伯耀を代理人として鹿島建設との交渉がはじまる。そして同年七月五日、来日した耿諄らと鹿島建設との「共同発表」が行われた。
しかし鹿島建設は、「共同発表」のすぐ後、記念館の設立は認めない、賠償は認められない、供養料として一億円以下を出すことはあり得る、「謝罪」は「遺憾」の意味で「日中共同声明」によって中国側の賠償請求権は放棄されている、と主張しつづけた。
そんな鹿島建設の態度を許すわけにはいかず、耿諄を原告団長とする被害者・遺族十一名は一九九五年六月、鹿島建設に損害賠償を求めて東京地裁に提訴する。原告が望むのは「討回歴史公道」のみ。要求は「公開書簡」で記した三つの条件だった。
だが東京地裁は一九九七年十二月、原告の訴えをしりぞける。理由は、「訴追期間二十年を過ぎている」というものだった。納得のいかない原告側はただちに東京高裁に控訴。翌九八年七月から公判がはじまった。とはいっても、原告の証人尋問もなされないまま九九年六月、新村正人裁判長は協議に入ることを告げ、原告側と鹿島建設との和解に向けた話し合いに入った。
謝罪なき和解――「花岡和解」
一九九九年八月、新美弁護士は北京で耿諄らに会い、鹿島建設との和解を強くすすめた。そして、それをすすめるためにも自分たちに「全権委任してほしい」と原告団に要請している。耿諄団長は、鹿島が「共同発表」後すぐから謝罪をくつがえす主張をしていることを知り、和解の条件は「鹿島の謝罪」を第一とする「公開書簡」に記した三つの要求を満たすこと、と確認し原告らがサインした。
二〇〇〇年四月二十一日、東京高裁は「和解勧告書」をだした。が、「和解勧告書」をみると「花岡殉難烈士記念館の建設」が記されておらず、この内容で和解することに耿諄団長は強い不満を感じていた。そして八月、ふたたび和解に応じるよう中国まで説得にきた新美弁護士らと耿諄は、つぎのような会話をしている。
《「もし裁判に負けたら、弁護団にはどんな損害があるのですか」「いや、何の損害もない」と新美氏。
耿諄さん、「もし、弁護団にも何の影響も無いのなら、裁判に負けよう、たとえ負けても妥協しません。歴史的に私たちが踏みとどまるなら、我々は道義の上では勝利したことになります……たとえ裁判で敗訴しても、政治的、歴史的には勝訴したことになり、百年後でも私たちは彼らの罪行を暴露する権利があるのです」》
(旻子著『尊厳』より)
耿諄の生き方は、尊厳を守ることにつらぬかれている。この被害者・遺族たちと対等に生きようとする弁護団なら、ここで和解を拒否する道を選んだかも知れない。が、新美ら日本の代理人弁護団は、「彼らのために私たちが和解してあげる」ことが「善意」だと、原告らの意思を無視して鹿島建設との和解をすすめた。
二〇〇〇年十一月二十九日、東京高裁で和解が成立。マス・メディアはその「和解」を、「戦後補償で最高額」「日本の戦後補償を実現していく上で画期的な和解」と報じた。
ほんとうに画期的なのか、その「和解条項」をみてみよう。
関西学院大学教授・野田正彰の取材によれば、「この和解は、弁護団側の独断によるもので、原告の本意ではなかった」という。たしかに新美ら弁護団は、「和解条項」の一《当事者双方は、平成二年(一九九〇年)七月五日の「共同発表」を再確認する》に続く《ただし、被控訴人は、右「共同発表」は被控訴人の法的責任を認める趣旨のものではない旨主張し、控訴人らはこれを了解した》という文言を原告団に伝えなかったばかりか、原告たちに中国語の訳文すら渡さなかった。
鹿島の心からの謝罪を求めている原告たちに、「鹿島が法的責任も認めず謝罪もしないことを原告が了解した」とする文言は、さすがの代理人弁護団も示せなかったのだろう。だからそれを〈かくし〉、原告団が納得する説明だけをして賛同してもらい、「謝罪なき和解」を成立させたにちがいなかった。
耿諄団長らは、代理人弁護団の説明をうけてたしかに「和解」に賛成した。が、後日、「和解条項」の真の内容を知った耿諄は、「だまされた!」と怒髪天をついて床にふす。また、被害者遺族で原告のひとりである孫力は二〇〇一年六月、「花岡事件『和解』の欺瞞を告発する」声明を発表。さらに同年十一月二十六日、日本の原告代理人弁護団に対して「公開書簡」を送っている。「声明」も「公開書簡」も原文は中国語だが、それを翻訳した山邉悠喜子、張宏波(チャン・ホンボ)の許可を得てここに両文、全文を紹介しておこう。
声明:花岡事件「和解」の欺瞞を告発する
公開書簡:花岡訴訟原告弁護団弁護士への公開書簡
ふたつの文章を読めば、野田正彰の言葉を待つまでもなくこの「和解」が、日本の代理人弁護団がわの独断によるものだったことが明らかであろう。それにしても、原告の意思に最も忠実でなければならない代理人弁護団が、なぜ原告の意思を無視して「和解」をすすめてしまったのだろう。これでは花岡被害者に対する二重の加害ではないのか。また、このような中国人原告たちが否定する「謝罪なき和解」を、戦後補償の「画期的な和解」と自賛するのは、まともなことなのだろうか。
国も企業も加害責任を認めない、謝罪もしない「花岡和解」については、花岡問題の研究者で知られる大館市在住の野添憲治をはじめ、山邉悠喜子、張宏波、金子マーティンなどが「和解」直後からその問題点を指摘していた。そして二〇〇七年六月十九日付「毎日新聞」夕刊に、野田正彰の「謝罪なき和解に無念の中国人原告――花岡事件が残した問題」と題する寄稿が掲載されたことから、「花岡和解」の深刻な問題が広く世間に知られるようになった。
一連の記事やコラムで野田は、原告代理人弁護団は「どこかで妥協し、カネを貰っていくのが幸せなのだ」と確信して疑わず、原告の意思、尊厳を軽視したと批判する。そして、《花岡和解問題は、弁護士や支援者の多くが耿諄さんの生き方を理解できなかったことにある。こんなに大切な他者を、本当に発見することができなかった。鹿島裁判に始まる戦後補償運動すべてが振り帰らなければならない問題である》(野田正彰『虜囚の記憶』みすず書房より)と指摘する。
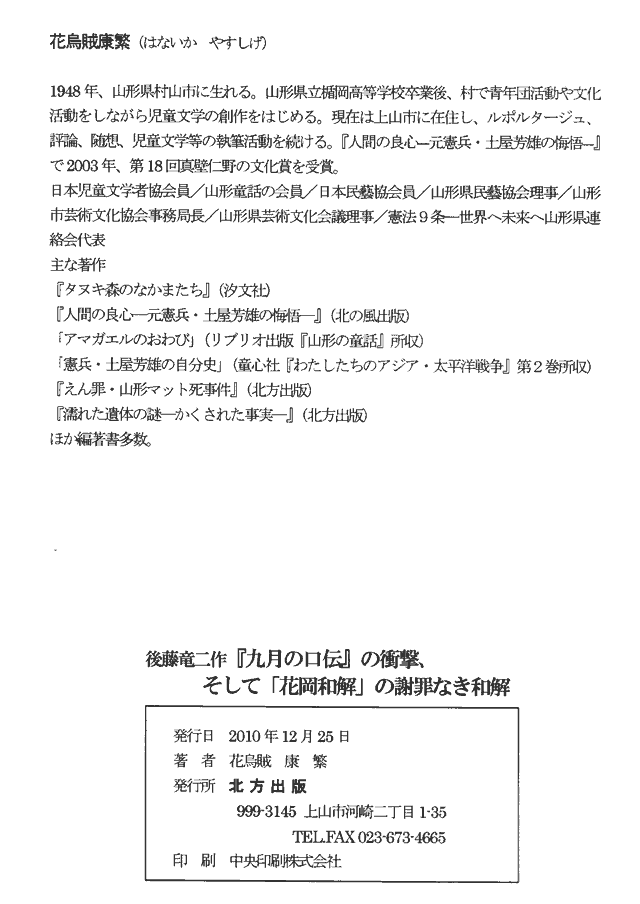
『世界』(岩波書店)二〇〇九年九月号の「『花岡和解』を検証する」(内海愛子ほか)では、《弁護団は…(略) …和解条項全般について、特に和解条項第一項を但し書きを含めて逐次日本語で説明していたことが確認される。弁護団が和解条項について故意に説明を省略した事実は認められない。と同時に、通訳は逐語通訳されていない。特に…(略) …〔但し書きにあたる〕重要な一句は通訳されていなかったことも確認された》(288~289p)としながらも、《弁護団が故意に説明を省略して原告らを『欺いた』との指摘は当たらないと判断する。》(292p)と結論づけた。
こんな道理のない検証は茶番だ。故意であろうが過失であろうが、代理人弁護団が原告に「和解条項」を逐次通訳せず、中国語訳文を渡さなかったのは事実。「だまされた」と訴える原告がいるかぎり検証は、原告側の立場からなされるべきだった。が、『世界』は、あえて代理人弁護団側に立って検証し、原告と読者を新たにあざむいている。『世界』も墜ちたものだと思うのは、私だけだろうか。
今年二〇一〇年、「花岡和解」から十年を迎えた。
しかし代理人弁護団は、原告である耿諄や孫力の訴えにいまだ何ひとつ答えることなく、彼らを無視したままだ。日本でも「民主的」かつ「人権派」と目されているこの人たちの文化を、そして「花岡和解」を画期的と自賛する私たちの文化を、改めて問い直さなければ、戦後を拓くことはできないのかもしれない。
野添憲治20101001耿諄さんを訪ねて
花岡事件の中国人指導者の今

9月初めに中国へ行き、アジア・太平洋戦争の時に大館市で起きた花岡事件の指導者・耿諄さんを訪ねるため、河南省の鄭州空港から車で襄城県に向かった。15年前にはじめて行った時はバスで7時間だったか、高速道路で2時間で着いた。
わたしは27歳から花岡事件の取材をはじめたが、疑問の一つに花岡鉱山の鹿島組(現鹿島)花岡出張所に来た約千人の中国人強制連行者の大隊長で、花岡蜂起を指導した耿諄さんか、横浜裁判で花岡事件が裁かれる前に中国へ帰ったまま行方不明になっていることかあった。その耿諄さんか中国にいることがわかり、1987年に46年ぶりに来日した。この時に東京から大館まで案内したのが、最初の出会いだった。その時の印象は「古武士のような好好爺」だった。
その後、中国や日本で何度か会っているうちに、耿諄さんの伝記を書こうと考えた。許可をとると河北大学の張友棟教授に通訳をお願いし、92年に襄城県に行って予備取材をした。95年には14日間滞在して取材し、翌96年にも7日間いて補足の取材をした。日本語版は三一書房から出版になり、中国語訳の『耿諄伝』が河北大学出版会から出た2000年5月には同県主催の出版記念会があり、家族とともに同県に行った。2日かかりの盛大なもてなしを受け、耿諄さんとの友好はいっそう深まった。
しかし、耿諄さんを代表とする原告11人が鹿島に損害賠償請求訴訟を提起し、東京高裁から和解による解決か提案されていたか、この年の11月29日に和解が発表された。だが、「和解条項」の内容と鹿島のコメントを知った耿諄さんは、昏倒して入院した。そして基金の受け取りを拒絶し、「私は花岡と縁をきったのです」(晃子著『尊厳』=日本僑報社)として、その後は沈黙を守った。
日本人には会わないという風評が伝わったが、その後も年賀状は毎年届いた。わたしも新しく花岡事件関係の本か出ると送った。昨年のはじめころから、「耿諄さんは君に会いたがっている」という伝言が数人から届いた。わたしも直接に和解前後のことを聞きたいと思っていた。そして昨年末に訪ねることに話がまとまったが、わたしの急病で計画はつぶれた。
ことしの2月に耿諄さんは脳梗塞で倒れ、4月まで入院した。すぐに行きたかったが、わたしの体の回復が遅れているうえに、中国の夏の暑さが日本と同じに厳しいのでのぱし、9月1日にようやく成田空港から飛び立った。そして10数年ぶりに再会したのだか、その前に耿諄さんの略歴を簡単に紹介したい。
耿諄さんは今年96歳。1914年に襄城県の裕福な家に生まれたが、のちに一家は匪賊に襲われて無一文になった。通っていた塾をやめて古本屋をやり、18歳で国民党の兵士になった。読み書きかできるので数年で上尉連長になり、洛陽戦役で負傷して日本軍の捕虜になり、俘虜収容所を転々とした。その後青島から日本に送られる途中に、中国人強制連行者300人の大隊長に指名された。
下関に上陸し、花岡鉱山の鹿島組花岡出張所に着いたのが44年8月で、中山寮に入って働いた。食糧が少ないうえに冬も夏服、補導員たちはこん棒で殴った。45年に新しく683人か来たものの死者が続出し、「死守よりない」と考えた耿諄さんの指導で6月30日の夜に蜂起した。欣淳さんは自殺を図ったが助けられ、捕らえられた。秋田刑務所で殴る蹴るの尋問を受け、何度も脳しんとうで倒れた。
日本の敗戦後は花岡裁判の証人として東京の中野刑務所に移ったが、尋問された時の傷か痛むので中国に帰された。職がなく奥地で農業をやったが、文化大革命で痛めつけられた。84年に中国政治協商会議襄城県委員会の常任委員になり、30年ぶりに同県に戻った。日本を訪れて帰ると、公務のかたわら鹿島との裁判に没頭したが、和解は耿諄さんの望んだ内容ではなかった。
9月2日に自宅を訪ねると、耿諄さんはベッドヘ横になっていた。わたしを見ると「おーう」と言って起き上かろうとしたが、起き上がれなかった。握手のあと日本から持参した『耿諄伝』など9冊を枕元に並べると、手にとってなつかしそうに見ていたが、「あなたの本は中日の懸け橋です。過去のその歴史はもう言いません」と言って目をつぶった。
襄城県には4日間滞在したが、それ以上話を聞けないまま帰国した。耿諄さんがまた元気になり、再会できることを祈りながら―。
のぞえ・けんじ1935年藤里町生まれ。著害に「花岡事件の人たち」など。社会評論社から第1期・第2期著作集全10巻がある。能代市。
福田昭典20100726毎日新聞夕刊「謝罪と保証へ舵を切れ」
日本企業の世界戦略のためにも 元連合国捕虜虐待問題

五月十日の毎日新聞夕刊は、「全来パターン・コレヒドール防衛兵の会」元会長であるレスター・テニー氏が元連合国捕虜を使役した日本企業へ謝罪を求めた手記を掲載した。本稿では、テニー氏の手記を受けて、日本企業の謝罪がなぜ必要かを改めて述べたい。
筆者は一九九九年十二月、「戦争犯罪と戦後補償を考える国際市民フォーラム」の証言者として来日した氏とお会いする機会を得た。いつも満面に笑みを湛えていたか、証言はむごたらしく、「日本人は犬を棒で打ったり蹴ったりはしないのに、捕虜に対しては平気で殴り蹴った」と語り、「大企業の三井が、かつて戦争捕虜に対して行ったことを何も知らせず、教えようとしていない」と告発した。
テニー氏は手記で、藤崎一郎駐米大使が昨年五月、元捕虜の人々に「途方もない損害と苦しみを与えたことを心から謝罪」したことを、名誉ある解決を図るものと評価しつつ、日本経団連の御手洗富士夫会長(当時)へ謝罪を求めた手紙が無視された、とも記している。
藤崎大使の誠実な対応と比べ、テニー氏の手紙に返答しない御手洗氏の対応は、日本経団連の歴史事実への不誠実さを際立たせる。テニー氏はさらに、三井、三菱、川崎、日本車両、日立などの企業で捕虜が奴隷労働を強いられた、とつづった。
注目すべきは、名指しされた各社が米国各地で計画中の巨大な社会インフラ整備である高速鉄道建設プロジェクトヘの入札参加を表明し、日本政府と密接な連携をもって積極的な営業活動を展開する我が国の代表的な企業であることだ。
二日後の五月十二日、毎日新聞朝刊は、米国高速鉄道に絡む日本の企業と政府が一体となった売り込みを特集記事で報じた。「新幹線、リニア 米に売り込み」「官民一体で積極策」「内需限界 海外に活路」の見出しが躍っていた。
日本車に捕らえられた米軍捕虜の四〇%が「外地」「内地」の捕虜収容所で死んだ歴史事実に、日本政府とかつての使役企業は真摯に対応すべきである。政府が元捕虜のために追悼碑一つ建てず、強制労働を課した企業がその事実さえ認めない現実は、あまりに異常である。テニー氏の手記は、米国の公共工事へ参入するためには、日本の政府と企業が歴史認識を改め、戦後補償をなすべきである、という警告に聞こえる。
問題解決の手本はある。米国の高速鉄道網建設プロジェクトの強力なライバルであるドイツが、ナチス体制下で旧ソ連邦、ポーランドをはじめとする欧州各地から強制連行し、強制労働を課した被害者の補償のために、官民それぞれが五十億マルク、総計百億マルクを拠出し、二〇〇〇年八月に設立した強制労働補償基金「記憶・責任・未来」がそれである。現在までに約百七十万人への補償金の支払いを終えている。
他方日本では、二〇〇〇年十一月に東京高裁で鹿島建設花岡裁判の歴史的な和解が成立して以降、戦時中の強制連行・強制労働問題の解決は途絶えていた。しかし、昨年から今年にかけて西松建設が関わる二つの強制労働裁判(広島県安野発電所・新潟県十日町発電所)で企業の謝罪と補償(安野では記念碑建立を含む)を内容とする和解が成立した。画期的な事例を前に、政府も企業も大きく歴史の舵を切るべき時である。
三井・三菱の鉱山現場で撮られた、元捕虜の骨と皮だけの痩せこけた写真が残されている。この写真が米国のマスメディアに取り上げられた際の反響を想像できる経営者であれば、「歴史問題」の放置が自社の世界戦略にとっていかなるリスクであるかも理解できよう。
テニー氏の訴えに、日本経団連の米倉新体制と各企業経営陣が迅速に対応するよう求めたい。
(ふくだ・あきのり=中国人強制連行を考える会事務局長)
福田昭典「元連合国捕虜虐待問題 謝罪と補償へ舵を切れ」(2010年7月26日付夕刊)を読んだ。同記事は、日本企業による捕虜虐待を経験したアメリカ人の主張を引き取り、「日本の政府と企業が歴史認識を改め、戦後補償をなすべきである」と主張している。その「問題解決の手本」として、ドイツの基金のほかに、日本における鹿島花岡「和解」、および西松和解を紹介している。日本で成立したこれらの「和解」には、福田氏が事務局長を務める「中国人強制連行を考える会」が主要な支援団体としてかかわっている。
しかし、2007年6月19日付の貴紙夕刊に掲載された野田正彰氏の記事(「謝罪なき和解に無念の中国人原告 花岡事件裁判が残した問題」)、「信濃毎日新聞」に掲載された同じ野田氏の記事「信濃川強制連行和解拒否」(2010年4月2日付)などで指摘されているとおり、花岡「和解」や西松和解に対しては被害当事者の側から受け入れ拒否の声があがっている。その理由は、加害企業が強制労働の歴史的事実もその責任も認めておらず、したがって拠出された金銭は賠償金・補償金の性格を持たないからである。こうした立場から批判する被害当事者にとって、2つの和解は、「歴史的な和解」でもなければ「画期的な事例」でもない。福田氏のいう「企業の謝罪と補償を内容とする和解」という評価とは正反対である。こうした被害当事者が存在することは、他ならぬ福田氏がもっともよく知っているはずである。
もちろん、いずれの和解においても、受け入れた当事者がいるのは事実である。問題はそこにはない。受け入れた被害者がいる一方で、明確に受け入れを拒否している被害者がいるにもかかわらず、その声に耳を傾けることなく、「画期的」「歴史的」と自賛を繰り返す支援者の姿勢こそ、問わねばならない。支援者の努力がいかに大きなものであったとしても、和解をどう評価するかは支援者が行うことではなく、原告・被害者自身が行うことである。ましてや、原告団長や元原告らが「和解」の内容を受け入れないという拒否声明まで出しているのである。花岡「和解」では、耿諄・原告団長は「弁護団に騙された」とも訴えている。「和解」を受け入れた人たち以上に、受け入れなかった人たちに真摯に対応するのが、本当の意味での「支援活動」ではないか?
福田氏は、鹿島花岡訴訟の原告団長となる耿諄氏に初めて会った時(1987年)の印象をこう回想している:「仙人が現れたみたいだった。オーラというか、何かしなければと感じて」(『朝日新聞』2000年12月8日2面)。耿諄氏が「和解」を拒否していることに対しても「何かしなければと感じ」なければ、花岡「和解」は「問題解決の手本」にも「歴史的な和解」にもならないはずである。
石田隆至
鎌田慧20100706東京新聞「前事不忘」
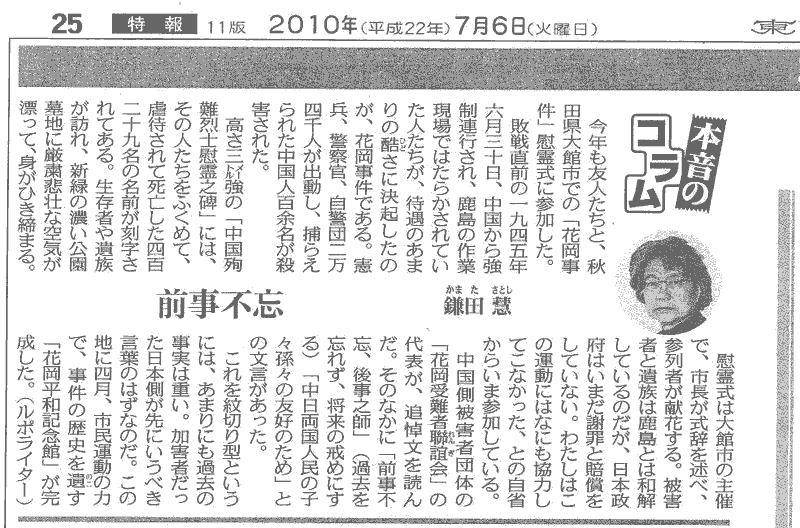
今年も友人たちと、秋田県大館市での「花岡事件」慰霊式に参加した。
敗戦直前の一九四五年六月三十日、中国から強制連行され、鹿島の作業現場ではたらかされていた人たちが、待遇のあまりの酷さに決起したのが、花岡事件である。憲兵、警察官、自警団二万四千人か出動し、捕らえられた中国人百余名が殺害された。
高さ三メートル強の「中国殉難烈士慰霊之碑」には、その人たちをふくめて、虐待されて死亡した四百二十九名の名前か刻字されてある。生存者や遺族か訪れ、新緑の濃い公園墓地に厳粛悲壮な空気が漂って、身がひき締まる。
慰霊式は大館巾の主催で、市長が式辞を述べ、参列者が献花する。被害者と遺族は鹿島とは和解しているのだか、日本政府はいまだ謝罪と賠償をしていない。わたしはこの運動にはなにも協力してこなかった、との自省からいま参加している。
中国側被害者団体の「花岡受難者聯誼会」の代表が、追悼文を読んだ。そのなかに「前事不忘、後事之師」(過去を忘れず、将来の戒めにする)「中日両国人民の子々孫々の友好のため」との文言かあった。
これを紋切り型というには、あまりにも過去の事実は重い。加害者だった日本側が先にいうべき言果のはすなのだ。この地に四月、市民運動の力で、事件の歴史を遺す「花岡平和記念館」が完成した(ルポライター)
教師の号令で国民学校四年生だった野添憲治さん(75)は、繰り返し叫んだ。「チャンコロのバカヤロー」。縛られて座っている二人の中国人に砂をかけ、つばを吐くと、村人から元気がいいとほめられた
▼六十五年前の六月三十日深夜、秋田県の花岡鉱山の河川改修現場で、鹿島組から過酷な労働を強いられた中国人約八百人が抵抗に立ち上がった。戦後に「花岡事件」で知られる一斉決起である
▼野添少年が見たのは、この時に山を越えて逃げた人だった。軍国少年だったが加害者ではなかったという信念は崩れ、戦後は現地での聞き取り調査など事実の発掘に傾倒した
▼山にこもった中国人は鎮圧され、三日三晩縛られたまま、水も食事も与えられなかった。それ以前に病死や虐待死した中国人も含めると、鹿島組の下で働いた九百八十六人のうち四百十八人が亡くなった
▼戦時中、百三十五の事業所に強制連行された中国人は約四万人。死亡者は七千人近くに上る。花岡事件が二〇〇〇年、東京高裁で和解した後、すべての現場を歩こうと野添さんは慰霊と取材の旅を始めた
▼九年かけて炭鉱の跡など全国を歩いた。記録も記憶も失われている事業所が多かった。「そんなことを聞いてどうする」と怒る人もいた。時間をかけて丹念に歩くと、問い掛けが聞こえてきたという。<日本人は、何をしなければならないのか>
石田隆至20100627東京新聞編集部御中 pdf
大学で教員をしております石田隆至と申します。
貴紙5月7日付の渡邊澄子氏「恐るべき人権無視 花岡事件」、6月22日付の内田雅敏氏「花岡和解から西松和解へ」、そして本日27日付「筆洗」コラムでの野添賢治氏の紹介、いずれにもたいへん興味をもって拝見しました。昨年10月3日にも野田正彰氏へのインタビュー記事(『虜囚の記憶』で戦後責任問う 過ち直視し“叫び”を知る))が掲載されていました。この国の戦後処理が未完であることを考えれば、花岡事件も花岡「和解」も決して過去のことではないのだという貴紙の透徹した歴史観に、深く敬意を表しております。
ただ、担当弁護士でもあった内田氏の文章には、違和感を覚えるところがあります。22日付の記事でも、原稿代表・耿諄氏を中心とする写真が掲載され、「和解案受け入れを決めた翌日」とわざわざ説明文が付されていますが、御存知の通り、耿諄氏は「和解」成立後、その受け入れを拒否するようになりました。耿諄氏の写真を掲載しながら、この不可解な事実には一切触れない内田氏の姿勢には大いに疑問を感じます。しかも、和解を拒否しているのは、原告.. 11人のうち、原告団長の耿諄氏のほか、孫力氏、孟繁武氏(「和解」成立直前に逝去、遺族が受け入れ拒否)と.. 3名もいるのです。
なぜ耿諄氏らは「和解」の受け入れを拒否するようになったのでしょうか? 事前に内田弁護士を含めた弁護団から説明を受けていた「和解」の内容と、後日実際に目にした和解条項との間には大きな開きがあったからです。つまり、和解成立後に初めて読んだ和解条項で、原告の三要求である「責任を認めて謝罪」「記念館の建設」「賠償金」が一つも達成されていないことを知ったのです。和解成立前には、記念館建設以外は原告の要求が達成されるとの説明を聞かされていたにもかかわらず。しかも、弁護団は和解条項の最終案を原告に事前に示すことをしませんでした。受け入れを拒否する原告が現れるのも当然のことです。
こうした事情を考えれば、内田氏の記事の展開は非常に恣意的です。たとえば、原告にとってもっとも根本的な要求である「責任を認めて謝罪」について見てみます。22日付の内田氏の記事では、和解条項第一項のなかで.. 90年の「共同発表」の内容が再確認されていることのみ触れられていますが、原告もこの点はまったく問題にしていません。原告らが問題にしているのは、その第一項に付加された「但し書」です。つまり、第一項は次のようになっているのです。
一 当事者双方は、平成二年(一九九〇年)七月五日の「共同発表」を再確認する。ただし、被控訴人は、右「共同発表」は被控訴人の法的責任を認める趣旨のものではない旨主張し、控訴人らはこれを了解した。
この但し書きを見れば、加害企業・鹿島がその法的責任を認めていないのはもちろんのこと、被害者原告までそのことを了解したことになっているのは明白です。鹿島に法的責任がないことを認めてしまっては、原告にとって何のための訴訟だったのか分からないことになります。
ところが、内田氏は記事の中で、原告が問題視したこの「但し書」については一言も触れていません。内田氏が引用した「共同発表」には「中国人が花岡鉱山出張所の現場で受難したのは、閣議決定に基づく強制連行・強制労働に起因する歴史的事実であり、鹿島建設株式会社はこれを事実として認め企業としても責任があると認識し」とあり、確かに鹿島は強制労働の事実を認めてその責任を認識しているといえます。ところが、「但し書」が付加されることで、法的責任は否定されていますので、「共同発表」を再確認したことは無効になっています。
この理解しがたい和解条項第一項の論理矛盾とそこから引き起こされた原告の受け入れ拒否について、耿諄氏らは説明を求めているにもかかわらず、内田氏ら弁護団はいまだにきちんと説明をしていません。内田氏らにとって、「和解」受け入れを拒否する原告などまるで存在していないかのような扱いです。にもかかわらず、このように耿諄氏の写真を使って花岡「和解」を擁護し、さらにその後の西松和解まで擁護するというのは何を物語っているでしょうか? 被害者の尊厳回復・人権擁護のために始めたはずの戦後補償運動が、いつしか内田氏ら支援者らのための、弁護団が主人公の運動に変質してしまっているといわざるをえません。
5月7日の渡邊氏の寄稿も、昨年インタビューに答えた野田氏も、そして今日のコラムで紹介された野添氏も、いずれもこの運動が何のためのものだったかを問い直しています。そういう意味で、内田氏の寄稿のみ異質です。原告から委任されて法廷闘争をしたはずの内田氏らが、もっとも原告の思いから遠いところにいたというのは皮肉では済まされない、日本社会が抱える根深い問題のようです。野添氏の言葉、<日本人は、何をしなければならないのか>がますます重く響きます。
なお、詳細は以下の拙稿を参照して頂きたいと思います。石田隆至・張宏波「東アジアの戦後和解は何に躓いてきたか?:『全面解決』における『謝罪』について」『戦争責任研究』66号、2009年.. 12月、20-31頁。
石田隆至(いしだりゅうじ)
内田雅敏20100622東京新聞「花岡和解から西松和解へ」

今年もまた六月三十日が近づいて来た。
六十五年前、敗戦間近いこの日、秋田県花岡鉱山鹿島組出張所で強制労働させられていた中国人らが、その奴隷労働に抗し、蜂起した。憲兵隊、警官隊、地元住民らによって鎮圧され多数の死傷者を出した。一年未満の間に強制連行された中国人九百八十六人中、四百十八人か死亡していることからその労働の苛酷さがうかがえる。
二〇〇〇年十一月、東京高裁で加害者鹿島建設と中国人受難者・遺族らとの間に和解が成立した。和解条項一条は[中国人が花岡鉱山出張所の現場で受難したのは、・・・強制連行・強制労働に起因する歴史的事実であり、鹿島建設はこれを事実として認め、企業としてもその責任があると認識し、当該中国人及びその遺族に深甚な謝罪の意を表明する」とした一九九〇年七月五日の共同発表を再確認している。和解案を受け入れることを決めたとき、花岡で父を亡くした遺族の楊さんか「今まで何度も会議をして来たが、今日の会議か一番うれしい」と語ったのを忘れることはできない。
昨年十月、西松建設広島安野中国人強制連行・強制労働-太田川から安野発電所への導水トンネル掘削工事-事件でも和解が成立した。花岡和解と同じ枠組みである。本年四月には、同社、信濃川ケースでも和解が成立した。このような積み重ねの延長上に、ドイツ型「記憶・責任・未来」財団のような全体解決も展望できる。
本年四月、花岡現地に「花岡平和記念館」が開館した。NPO法人花岡平和記念会の呼びかけにより、全国からの浄財によって設立された、加害の歴史を記憶する記念館だ。
遠くは一九五〇年代から花岡町長ら有志によって、そして八五年からは正式に大館市の行事として、地元の人々を中心として全国から市民運動家が参加し、中国からも受難者・遺族らをお招きし、毎年六月三十日、花岡蜂起の記念日に慰霊祭か行われてきた。草の根の交流だ。
今、西松の強制労働の現場、中国電力安野発電所の一角に中国人受難者・遺族と西松建設連名による記念碑が建立されようとしている。受難と加害の歴史を記憶するためのものだ。碑文には中・日両文字で「・・・西松建設は中国人受難者の要求と向き合い、企業としての歴史的責任を認識し、この姿勢を明確にした。太田川上流、安野発電所は、今も静かに電気を送り続けている。こうした歴史を心に刻み日中両国の子々孫々の友好を願ってこの碑を建立する」という一節が刻まれるはずだ。
(うちだ・まさとし=中国人強制連行花岡事件同西松事件代理人弁護土)
石田隆至20100723四谷総合法律事務所 内田雅敏弁護士殿 pdf
前略
大学教員をしております石田隆至と申します。『東京新聞』6月22日付の御寄稿「花岡和解から西松和解へ」を拝読しました。高く評価されるお仕事をされているのは存じておりますが、花岡「和解」の話になると、どうしてこのような記事を書かれるのでしょうか。内田先生のなかではどのように一貫性を保っておられるのか、奇妙な感覚にとらわれています。
花岡「和解」の評価をめぐっては、原告11名のなかに3名も、結果の受け入れを拒否されている方がいらっしゃることは、私が指摘するまでもないことです。担当弁護士としては、この事態をどのように解決すべきかとお悩みになり、ご心痛のことと存じます。
記事中にお使いになっている写真では、その3名のうち原告代表でもあった耿諄氏が正面に大きく映っています。写真の下の説明書きでは、「和解案受け入れを決めた翌日、・・(略)・・2000年4月30日」とあります。この写真と説明書きは、“原告たちは和解案を受け入れて笑顔を見せている”というメッセージを伝えています。しかし、少なくともここに映っている耿諄さんの現在のお立場はまるで逆です。和解を受け入れてもいなければ、非常に憤っておられるからです。
なぜ和解を受け入れず、憤っておられるのでしょうか? それは、和解成立前に口頭説明で聞いていた和解の内容と、和解成立後にはじめて読んだ和解条項の内容とが大きく異なっていたからです。鹿島は責任を認めて謝罪したと聞いていたのに、和解条項には鹿島は法的責任を認めず、そのことを中国人被害者・原告は了解したと書いてあると知れば、和解を受け入れられず、憤られるのは当然のことでしょう。
さて、原告が本当の和解内容を事前に知ることがなかったという異常な事態はなぜ起きたのでしょうか? これは内田先生ほか代理人の方々の手続きの進め方以外に理由はないでしょう。こればかりは鹿島の仕業にもできません。したがって、耿諄さんら「和解」の受け入れを拒否している原告たちに、きちんとした説明を行う義務を有しているのも内田先生たち代理人の方々以外にないといえるでしょう。
まもなく「和解」から10年です。内田先生や故・新美隆先生は、「和解」後も、同和解に関して少なくない文章を発表されてきましたが、受け入れを拒否している原告の方々に正面からお答えになるために、どのくらいその紙面をお使いになってこられたのでしょうか? 管見では、その大半が、いかに「和解」が意義あるものであったかに関する内容で占められているように思われます。
今回の『東京新聞』の記事の、特にこの写真と説明書きには、和解後に内田先生がお書きになってきた内容が凝縮されているように思います。この写真の使われ方が、現在の耿諄さんのお立場をまったく配慮していないものであることは既に述べましたが、2000年4月の写真に「和解案受け入れを決めた翌日」という完全に誤った情報を付加したことは、「和解」成立時の欺瞞を再生産してはいないでしょうか? この写真が撮られた2000年4月に原告たちが内田先生ら代理人から報告を受けたのは、「和解勧告書」についてです。中国語に訳された同勧告書を原告たちは読みながら、「和解」という形の解決となることを受け入れたのです。この「和解勧告書」は4項目にとどまり、具体的な条項については「更に検討する」と記されてあるとおり、内容的な詰めはこれからで、基本的方向性だけが記された文書です。つまり、2000年4月段階で原告たちが同意したのは、和解という解決方式および基本原則についてだけでした。しかし、この写真が「和解勧告書の受け入れ」に伴うものであるという断りは一切なく、本文の文脈からも、最終的な結果についての言及であると読むしかない内容になっています。
通常であれば、「和解勧告書」から最終的な「和解条項」がまとまるのにはそれほど時間がかからないケースもあるそうですが、花岡和解では、7ヶ月以上を要しました。当然ながら、最終的にまとまった和解条項の内容が、和解勧告書段階からはかなりの距離があることを示唆します。和解条項は項目的にも8項目に増え、分量も3倍程度になっています。中国人被害者たちがもっとも重視していた「謝罪と責任」についても、第一項で但し書きが付加されました。この7ヶ月間の交渉が相当難航したことは、新美弁護士が何度も書いておられます。これだけを考えても、4月の「和解勧告書」と11月の「和解条項」が同内容であったとはおよそ考えがたいものがあります。新美弁護士は(内田先生もそのようですが)、それでも「和解勧告書」と「和解条項」は「趣旨においては変わりはない」とお考えですが、それを最終的に判断するのは代理人ではなく、当事者の原告であるはずです。しかし、その判断の機会を原告は奪われました。まとまっていた和解条項の最終案が原告に見せられることがなかったからです。和解条項を見せなかった事実は林伯耀氏が明らかにしておられますが、代理人のお一人として、どうして見せないことにしたのかについて、いまだ説明責任を果たされていないと考えています。次に文章を発表されるときには、是非お願いしたいところです。
『東京新聞』の記事に話を戻します。繰り返しますが、写真下には「和解案受け入れを決めた翌日」と書いてあります。この表現は、文字通り読めば、記事本文の文脈からいって、最終的な和解案を受け入れて原告らが安心した笑顔を見せている、という意味以外の理解が生まれがたいものになっています。ここで内田先生がお使いになっている和解案というのが「和解勧告書」の段階であるとか、「交渉過程の一和解案」であると読むのは、この記事においては、深読みに過ぎるでしょう。和解という解決方針と基本原則を受け入れたに過ぎない段階の写真をもってして、原告が最終和解条項を笑顔で受け入れたと思わせる情報操作がなされているといえます。
記事本文でも同様の操作が行われています。第三段落にそれが端的に表れています。この段落は3つの文から成り立っていますが、第一文は2000年11月に和解が成立したことについて、第二文では和解条項第一項の前半部分について「共同発表」を引用して言及されています。ところが第三文では、「和解案を受け入れることを決めたとき」(傍点は引用者)に原告の楊さんが今までで一番嬉しいと言ったという内容になっています。この和解案というのは、先にも述べたとおり、和解勧告書のことです(『情況』稿でもそう書いておられます)。つまり、第二文までは和解成立時や最終和解条項に関する内容であるのに、第三文で紹介されている原告の反応は、7ヶ月前の和解勧告書に関するものです。これが誘導でなければ何なのでしょうか? そもそも、内田先生は11月には北京にいらしていませんので、和解成立直前の原告の反応を直接知りうることはできなかったはずです。
したがって、今回の記事に見られる記述の混乱は単純なミスではなく、意図したものでしょう。この写真が撮られた段階では、内田先生が強調される楊さんも、写真中央の耿諄さんも笑顔でいらっしゃるのはある意味で当然のことなのです。代理人である内田先生が新聞の紙面を割いて説明なさるべきなのはそのようなことではなく、この段階では喜んでいた耿諄さんたちが、なぜ和解成立後になって受け入れを拒否するまでになったのかについてです。耿諄氏も孫力氏も公開声明の形で内田先生に回答を求めているにもかかわらず、いつまでも沈黙されているのはどうしてなのでしょうか。
もちろん、内田先生はすでに回答をなさったつもりなのかもしれません。しかし、相手の求めるところに焦点を合わせた回答でなければ、その名に値しないことはいうまでもありません。これは、一般的な依頼でも当然のことですが、花岡事件訴訟の中国人被害者・原告は国際関係を背負った重要な依頼人ですのでなおさらです。では、内田先生らは、耿諄さんらの求めに誠実に対応されているといえるでしょうか? 最近の先生の文章を見ていますと、むしろ意図的に焦点が外され、すれ違いを望んでおられるかのような内容になっていると考えています。その象徴が、最近の先生の文章における和解条項第一項に関する扱い方です。2008年の『情況』稿あたりまでは、争点になっている第一項の但し書きに言及はされていましたが、今年1月の『信濃毎日新聞』での反論、3月の『自由人権協会』での報告文、そして今回の『東京新聞』の記事では、まるで但し書きなどなかったかのように、触れられることさえなくなりました。但し書きが争点になっているのに、そこに全く触れないというのは、よほど都合がお悪いのでしょうか?
いうまでもなく、この但し書きが付いた最終和解条項を、内田先生たちは、どういうわけか事前に原告に見せることはしませんでした。それが「和解」の受け入れ拒否を引き起こしたのです。これこそ、耿諄さんらが説明を求めている根本的な焦点であるのにもかかわらず、この点について内田先生は奇妙な沈黙を守り続けておられます。和解前にも和解後にも、この但し書きは触れてはならないテーマであるかのようです。鹿島が法的責任を認めないことを原告は了解したという鹿島全面勝利の内容ですから、触れられないのも当然ですが。
同時に、但し書きにおいて、鹿島は法的責任を認めないと明確に規定されているにもかかわらず、原告たちにはその事実を伝えることなく、逆に「共同発表」の精神は守られた、つまり、鹿島が責任を認めて謝罪したと説明していたことと、今回の記事は同一の構造を持っています。和解勧告書と和解解決への同意であったにもかかわらず、さも最終和解条項への同意であったかのように読めてしまう文章を公表して、再び耿諄さんら和解受け入れを拒否する原告を裏切り、読者をも操作しています。情報量に勝る代理人たちが、情報量の乏しい中国人被害者・原告や読者を相手に、事実に反する情報を提供して、言論の場を支配してしまおうとされています。これほど権力的な策動があるでしょうか?
勇気を持って誤りを正されることは、先生の名声を傷つけるものではなく、むしろ高めることであると考えております。率直に事実を認めて中国人被害者・原告と社会に対して謝罪され、鹿島とは異なる姿勢を見せて下さる日を心待ちにしております。
草々
2010年7月23日 石田隆至
追伸 花岡和解や西松和解に関して内田先生がお書きになったものは、ほとんど読ませて頂きました。ただ、直接お話を伺ったことはありませんので、私の理解が間違っている可能性もあります。先生さえよろしければ、直接お会いしてお話を伺いたいと考えております。ご検討下さいますと幸いです。
芹沢昇雄20100701「文化面・担当者」様
埼玉の読者です。
貴紙22日夕刊「文化面」の内田弁護士の記事に改めて抗議します。
紙面のあの「笑顔」の耿諄さんの写真は恐らく内田氏の提供と思います。
耿諄さんが「騙された」と怒り、未だに和解拒否していること彼は知りながら非常に「卑怯」です。知らない人は耿諄さんのこの笑顔の写真で本当に和解したと思うでしょう。
先日お伝えした通り、弁護団は「共同発表」の趣旨に則り和解と原告らに説明し、その時に「和解条項」を提示しないまま口頭で説明したのです。しかし、提示しなかった「和解条項」には共同発表には無かった【ただし、被控訴人は、右「共同発表」は被控訴人の法的責任を認める趣旨のものではない旨主張し、控訴人らはこれを了解した。】と追記されていたのです。耿諄さんたちは後日、これを知り「騙された」と怒ったのです。
この批判に内田氏は「口頭で説明した」と主張しましたが、その口頭説明でもこの「但し書」の追記部分が通訳されていなかったことが、当時の録画テープで確認されてい、これは岩波『世界』の検証でも確認しています。
この記事は、この裏切り騙しの上に、更に、耿諄さんの笑顔の写真で耿諄さんの怒りと和解拒否を隠すものです。この記事をこのまま放置することは貴紙がこの裏切り騙しに加担する事になります。地位や名誉を鵜呑みにしてはなりません。
ここに「共同発表、和解条項、公開書簡、拒否声明、孫力さん直筆声明」などを添付しました。必要なら資料はあります。
是非、反論記事を載せるべきです。
貴紙が「良心」があることを信じています。
花烏賊康繁20100629代理人の「反論」が示す原告無視! pdf
――野田正彰氏の「『花岡和解』から10年」とそれに対する弁護士・内田雅敏氏の「反論」を読む――
2010年1月15日付「信濃毎日新聞」夕刊のコラム「今日の視角」に、精神科医で関西学院大学教授の野田正彰氏の「『花岡和解』から10年」が掲載された。とは言っても、それを知らずにいた私は、読んでもいなかった。その約一週間後の1月21日、同紙に、「花岡裁判」の代理人である弁護士の内田雅敏氏が、「今日の視角『花岡和解から10年』への反論」を「寄稿」し掲載された。この内田氏の文章が掲載された「信濃毎日新聞」のコピーを、親友が送ってくれたので読み、これでは内田氏が「反論」している野田正彰氏のコラムも読まなくてはと、早速インターネットで文章をさがして読んでみた。
野田正彰氏と内田雅敏氏の文章を読んで、気づかされたことある。ふたつの文章を読むまで私は、「花岡和解」は日本の戦後補償裁判では「画期的」な成果と受け止めていたのだが、「花岡和解」には私たちの知らない問題があるかも知れないということだった。
「花岡和解」にはどのような問題があるのか……。先ずは「信濃毎日新聞」2010年1月15日付に掲載された野田正彰氏の「『花岡和解』から10年」と、同年1月21日付同紙に掲載された内田雅敏氏の寄稿「今日の視角『花岡和解から10年』への反論」をお読みいただこう。
内田氏はだれに「反論」しているのか?
野田氏、内田氏の文章を読み、読者はどのような感じを持たれただろうか?
野田正彰氏のコラムは、《日本と中国のマスコミで「花岡和解」と呼ばれて知られている事件がある》と書き出し、《「花岡和解」と別に呼ばれて問題にされてきたのは何故だろう》との自問にはじまる。野田氏は以降、鹿島組花岡事業所への強制連行と鹿島事業所での「花岡事件」、その中国人生残者と遺族らが「謝罪」と「損害賠償」を求めて鹿島を訴えた経過を概略的に説明。その結果としての東京高裁での「花岡和解」が、《鹿島の法的責任を問わず、賠償ではなく受難者の慰霊と支援のため5億円が信託されること》になり、《この和解条項に原告団が第一に求めた謝罪の言葉はなく、原告団長らは日本の弁護士たちに「だまされた」と声明して今に至っている》こと、そして幹事だった孫力さんが《訴訟を準備していた1993年の時点ですでに弁護士より、裁判で受け取るカネは弁護士、支援者、被害者で3等分すると聞いていた》という取材事実を報告している。結びの《「花岡和解」の過ちが謝罪されないものかと思う》は、おそらく、高齢の原告団長である耿諄さんたちをおもんばかる野田正彰氏の願いであろう、と私は読んだ。
一方、内田雅敏氏の「寄稿」は、タイトルからも分かるように野田正彰氏への「反論」である。しかし、野田氏のコラムを読めば読むほど、内田氏の「反論」は本当に「反論」なのかと首をかしげたくなる。
先ず、野田正彰氏のコラムが、内田氏を批判した「論文」なら「反論」はあり得るだろう。だがこのコラムは、どのように読んでも。随想もしくは短文のルポルタージュである。しかも野田氏はコラム中で、一度たりとも内田氏の氏名を出して批判してはいない。
確かに、弁護士は論争することが商売かも知れないが、野田氏のこのコラムに「反論」してしまったのは、内田雅敏氏の「まちがい」だろう、と私は思った。
「まちがい」にも、意図的な「まちがい」と過失による「まちがい」がある。そのどちらも、平常心を失った時に犯す。つまり、私たち新聞の読者には良いコラムと思われても、野田氏のコラムには、内田雅敏氏が平常心を乱してしまう記述があったということなのだろう。だからこそ内田氏は、「反論」として、わざわざ「寄稿」したのにちがいない。
ただ、私も物書きの末端にいるので分かるが、野田氏のコラムは「信濃毎日新聞」社から依頼されて書いているはずだ。一方、内田氏の「寄稿」は、新聞社への持ち込み、又は投書である。それを採用して紙上に掲載するかしないかは編集部の一存だが、「反論」すること自体がそぐわない野田氏のコラムへの「反論」は、一般的に考えればボツだろう。掲載したら編集部が笑われる。それなのに内田氏の「寄稿」は、きちんと掲載されている。いったい何故なのか……? 私には不可解この上ない。その不可解さがまかり通る内田雅敏氏という弁護士は、私たち庶民が持ち得ない力を持っていることだけは確かであろう。
さて、そんな力のある弁護士である内田雅敏氏が、平常心を乱れてしまう野田氏の文章はどこだろうかと探してみた。「これかな」と思われる箇所はいくつもあるが、《「花岡和解」の過ちが謝罪されないものかと思う》と結んだ箇所の「過ち」という言葉に、内田氏は意識せずとも心が乱れたのかも知れない。
なぜなら、「花岡和解」の「過ち」をおかしてしまう可能性があるのは、鹿島建設、代理人、原告の3者しかない。だが、原告団長の耿諄氏は《日本の弁護士たちに「だまされた」と声明》しており、「過ち」をおかした対象からは外れる。残るのは鹿島か代理人かということになる。いうまでもなく鹿島建設は、この事件では最初からの加害者だ。仮に「花岡和解」が鹿島有利となっており、それを「過ち」と指摘されても、鹿島の心が乱れることはないだろう。残るのは代理人である日本の弁護士たちということになる。
内田雅敏氏の「反論」は、冒頭で、野田氏のコラムには《以下の3点において重大な事実「誤認」がある》と記した。弁護士の先生がたの文章はこういう書き出しが一般的なのかどうか良く分からないが、感情むきだしの喧嘩腰の切り口である。それはさておき、では内田氏が、野田氏の何を《重大な事実『誤認』》と指摘しているかを見てみよう。
《野田氏は花岡和解には鹿島建設の謝罪がないと言う》――と内田雅敏氏は記した。
実は、私がすぐに野田正彰氏のコラムを探そうとしたのは、内田雅敏氏の「反論」のこの箇所を読んだからである。野田氏とは一面識もないが、元関東軍憲兵の土屋芳雄さんから戦争加害の聞き取りをしていたとき私は、野田正彰氏の『戦争と罪責』(岩波書店)を読み多くのことを学んだ。その野田氏が、もし「花岡和解には鹿島建設の謝罪がないと」言っているなら、そう言わざるを得ない客観的な事実関係を押さえてのことで、内田氏がいうような「誤認」とは信じられなかったからだった。
野田氏の文章を良く読んでほしい。野田正彰氏は《……この和解条項に原告団が第一に求めた謝罪の言葉はなく、原告団長らは日本の弁護士たちに「だまされた」と声明……》とは記しているが、野田氏自身が「鹿島建設に謝罪がない」などとは主張していない。
敏腕な弁護士であるはずの内田雅敏氏が、なぜこのような幼稚な読みまちがいをしてしまうのだろうか。いや、これは読みまちがいではなく、野田氏のコラムを読んだ内田氏が前段で指摘した通り平常心を乱してしまったからであろう。
内田氏が記した《野田氏は花岡和解には鹿島建設の謝罪がないと言う》という文章を、野田氏の文章にそって正確に書くとすれば次のようになる。
「原告団長の耿諄さんらは、花岡和解には鹿島建設の謝罪がないと言う」――しかし内田氏は、「原告団長の耿諄さんらは」という主語を、「野田氏は」に置き換えてしまった。あきらかにこれは「まちがい」である。弁護士である内田氏が、こんな重大な「まちがい」を内包した文章を、「反論」として「寄稿」してしまったとは……。
しかし考えてみれば、内田雅敏氏は、原告団長の耿諄さんたちから代理人に依頼された人だ。いくら平常心が乱れても、「原告団長の耿諄さんらは、花岡和解には鹿島建設の謝罪がないと言う」とは書けないだろう。裁判では、あくまでも原告が主であり、代理人は原告の意思に忠実でなければならない。極端にいえば、その原告たちの求めることがまちがいでも、代理人はその意思に従うのが常識で、代理人でありながら原告を公に「批判」することはあってならないはずである。
それにしても、原告団長の耿諄さんたちは、なぜ《日本の弁護士たちに「だまされた」》と声明しているのだろうか?
日本の弁護士、そのひとりである内田雅敏氏なら、詳細は知っていよう。「だまされた」と言われるのは心外にちがいない。しかし、「原告団長の耿諄さんたちには、重大な事実『誤認』がある」とはまちがっても記せない。
放っておくか……? その手もあるが、放っておいたなら、野田氏のコラムを読んだ読者が、日本の代理人弁護士たちが原告を「だました」という印象を持ってしまうだろう。内田氏はだいぶあせったのではないだろうか。あせらなかったら、ふてぶてしい人間ということになる。だからこそ内田氏は、本来なら「原告団長の耿諄さんらは」とすべきところを「野田氏は」に置き換え、《野田氏は花岡和解には鹿島建設の謝罪がないと言う》と書いてしまったにちがいない。
鹿島建設が原告受難者・遺族に謝罪した証拠として内田雅敏氏は、《和解条項1条は1990年7月5日の共同発表を再確認することから始まっている》と記した。そして「共同発表」文を引用している。
90年7月の「共同発表」も「和解条項」も私は目にしていなかったので、さっそく両方を全文、入手してみた。入手先は「私の戦後処理を問う会」のホームページである。できれば「共同発表」と「和解条項」の全文をここで紹介したいのだが、長文になるので内田氏が「反論」で引用している「和解条項1条」だけ全文を紹介してみよう。全文を読みたい方は「私の戦後処理を問う会」のホームページを訪問していただきたい。
- 平成9年(ネ)第5746号 損害賠償請求控訴事件
- 控 訴 人 耿 諄 外10名
- 被 控 訴 人 鹿島建設株式会社
- 和 解 条 項
一 当事者双方は、平成2年(1990年)7月5日の「共同発表」を再確認する。ただし、被控訴人は、右「共同発表」は被控訴人の法的責任を認める趣旨のものではない旨主張し、控訴人らはこれを了解した。
(2条以下略、下線筆者)
内田雅敏氏が記しているように、1990年の「共同発表」には確かに、《中国人が花岡鉱山出張所の現場で受難したのは、閣議決定に基づく強制連行・強制労働に起因する歴史的事実であり、鹿島建設株式会社はこれを事実として認め、企業としてもその責任があると認識し、当該中国人及びその遺族に深甚な謝罪の意を表明する》とある。そして、「和解条項」1条は、内田氏が記す通り《1990年7月5日の共同発表を再確認することから始まっている》のはまちがいない。
しかし、ここにも重大な「まちがい」、いや「ごまかし」があった。代理人内田雅敏氏があげた「和解条項」1条には、「1990年7月5日の共同発表を再確認する」に続けて、《ただし、被控訴人は、右「共同発表」は被控訴人の法的責任を認める趣旨のものではない旨主張し、控訴人らはこれを了解した》とあるではないか。
つまりこれは、鹿島建設が「共同発表」で声明したことは「法的責任」を認めたものではないと主張し、それを控訴人である耿諄さん外10名が了解したということだ。こんなことでは、原告団長の耿諄さんでなくても、「強制連行・強制労働に起因する歴史的事実……として認め、企業としてもその責任があると認識し、当該中国人及びその遺族に深甚な謝罪の意を表明する」と声明した1990年の「共同発表」は反故にされ、《日本の弁護士たちに「だまされた」》と思うのは当然のことではないだろうか。
代理人の内田雅敏氏が、「反論」の中で《ただし、被控訴人は、右「共同発表」は被控訴人の法的責任を認める趣旨のものではない旨主張し、控訴人らはこれを了解した》という重要な部分を隠し、ふれもしないのは、意図的な「ごまかし」と私は読む。
紙面の都合で……との言い訳は成り立たない。なぜなら、内田氏の「反論」は「信濃毎日新聞」社からの依頼原稿ではなく、「寄稿」だからだ。寄稿は、掲載を前提に書かれるものではなく、紙面の都合などへの配慮はいっさい無用である。
内田氏の「反論」は、「和解条項」などまったく知らなかった私に、それを知る大きなきっかけをつくった。墓穴を掘るとはこういうことであろう。内田氏は、野田氏が《和解は「日本の弁護士達にだまされた」》と言っているとも書いている。あえて説明するまでもないが、それも原告団長の耿諄さんの言葉である。
ここまでくると内田氏の「反論」の「まちがい」は、けっして「まちがい」ではなく、読者への「ごまかし」と言わざるを得ないだろう。そして内田氏のこの「反論」は、「反論」の名を借りて、野田氏を「重大な事実誤認者」に「でっちあげる」ための文章ではないかと、読者に邪推させてしまう危険性すらはらんでいる。
内田雅敏氏は、《確かに中国人当事者たちの中に和解を非難する人はいる。しかし、和解はこの非難者を含む、花岡受難者聨誼会で十分議論した上で、全員の賛成によって成立した》と記した。内田氏はこれを、誰に向けて語っているのだろうか。
何度も言うが野田正彰氏は、自分の言葉で「花岡和解」は弁護士たちに「だまされた」などとは、一言も述べていない。そう主張しているのは原告団長の耿諄さんたちであり、野田氏はそれを紹介しているにすぎない。したがって内田氏のこの文章は、原告団長の耿諄さんに、「あなたのいたところで十分議論した上で、全員の賛成によって成立したではないか」という意味に読み取れる。
《和解はこの非難者を含む、花岡受難者聨誼会で十分議論した上で、全員の賛成によって成立した》のが本当かどうか、私には判断できない。ただ、前段で指摘した内田氏の文章のさまざまな「まちがい」「ごまかし」から見て、ここにも何か「ごまかし」があるのだろうと考えてしまう。そうでなければ、《原告団長らは日本の弁護士たちに「だまされた」と声明……》するはずがないからだ。
仮に、内田雅敏氏が記した《和解はこの非難者を含む、花岡受難者聨誼会で十分議論した上で、全員の賛成によって成立した》のが真実なら、内田氏は、野田正彰氏に対して反論にならない「反論」を投げつけるのではなく、あなたを信用して代理人に依頼した原告団長の耿諄さんのもとに駆けつけることのほうが先ではないのか。なぜ内田氏はそれをしないのか……。「反論」ではそのことについてこそ述べて欲しかった。
和解金についての記述については、もう触れまい。ただ、内田氏の《その主張に添う中国人にだけ耳を傾け、和解を支持している他の多くの中国人の存在をことさら無視している》との野田氏への指摘は、内田氏自身が代理人であることを忘れてしまうほど平常心を失っている証拠だ。
花岡受難者やその遺族数百名が「和解」を支持していることは当たり前だ。それが代理人たちの「仕事」の評価にはならない。「和解条項」を良く見てみよう。「和解」したのは《控訴人 耿諄 外10名》である。その耿諄さん、あるいは幹事の孫力さんが「和解」を「だまされた」と非難しているのだ。
代理人である内田雅敏氏よ! あなたは「反論」の中で、その耿諄さんらをいっさい無視している。《その主張に添う中国人にだけ耳を傾け、和解を支持している他の多くの中国人の存在をことさら無視している》という内田氏の言葉は、裏を返せば、原告団長である耿諄さんたちを無視している内田氏の心の投影であろう。
この「反論」に内田氏は、《花岡事件、西松建設事件和解の中国人受難者側代理人弁護士》と表記している。「反論」はその立場で書いたことを示している。それは結構なことだが、その肩書きに物を言わせて、「花岡裁判」「花岡和解」の最も中心的な立場にいた原告団長の耿諄さんらを無視し、あげくに暗に指弾する文章を公に流布することは、許されるのだろうか? これは読者への問いである。
坪田典子20100628東京新聞夕刊 「文化欄」担当各位様 pdf
東京新聞編集部様、
6月22付夕刊5面文化欄、内田雅敏氏の記事「花岡和解から西松和解へ」について一言申し上げます。
わたくしは坪田典子と申します。大学で教員をしており日本の加害責任を研究課題としている者で、日本の加害認識に関する貴新聞の記事に日ごろより敬意を表している者です。
このたび、内田雅敏氏の記事「花岡和解から西松和解へ」を拝読いたしました。内田氏は花岡「和解」および西松安野「和解」に原告代理人弁護士として直接関わられた方として存じ上げています。しかし、当該記事は、事実が巧みにカムフラージュされており、読者に誤った事実を提供することにつながり、危惧しております。
たとえば、当該記事2段目に、「~1990年7月5日の共同発表を再確認している。」とありますが、実際の和解条項(2000.11.29)には、「共同発表を再確認する」の後に、「但し書」*が付加されています。そして、そのことによって、最初に提示された「和解」の内容(2000.4.21)が実質的に変化してきています。それゆえ、裁判を闘っていた原告代表の耿諄氏*を含む3人の原告(一人は和解直前の死亡により遺族が意思を継承)が、和解の受け入れを拒否しています。他にも和解受け入れを拒否している遺族がいます。内田弁護士は、自身がその代理人であったにもかかわらず、和解を拒否する原告や遺族が説明を求めても、和解後10年の今日に至るまで、一切応えることなく、「和解」拒否者たちは無視されている状態です。
また、上記引用に続く、「和解案を受け入れることを決めたとき~」とありますが、このとき原告側が受け入れたのは、2000年4月21日に東京高裁によって提示された「和解勧告書」で、これには上述の「但し書」はありませんでした。原告側が受け入れたのは、「但し書」が付加される前の文面です。そして、内田氏が引用している楊さんが喜んだという記述もまた、2000年4月の時点のことです。
2000年11月29日に、画期的とされて成立した花岡「和解」が、実はどのような内容で、原告被害者の意思がどのように無視された形で成立したものであったのかを、貴紙におかれましては、きちんと検証する必要があるのではないでしょうか。
どうぞ、この困難な時代に、鋭く事実を見抜く目と深い洞察を持って、歴史認識に対処されますよう、貴紙の良心に期待しております。私事ですが、過日、花岡「和解」をテーマに研究報告した報告原稿をお送りさせていただきたいと思います。花岡「和解」の理解への参考にしていただければと思います。なお、花岡「和解」に関する基本資料は下記をご参照ください。http://www.jca.apc.org/~hanaoka/
末筆ながら、貴社の今後のご発展を心より祈念いたしております。
- 注)*「但し書」:2000年11月29日に発表された「和解条項」第一項に付加されたもので、第一項は以下のようになっています。「当事者双方は、平成二年七月五日の「共同発表」を再確認する。ただし、被控訴人は右「共同発表」は被控訴人の法的責任を認める趣旨のものではない旨主張し、控訴人らはこれを了解した。」この「ただし」以下を「但し書」と呼んでいます。
- 注)*耿諄(コウ・ジュン)氏:耿諄氏は1945年6月30日の花岡蜂起のリーダーでもあり、80年代後半から、加害企業鹿島建設に対して、人間としての尊厳を求め、事実を認めて法的責任を認知し、謝罪を要求する闘いの中心人物でした。現在、ご健在です。
坪田 典子
芹沢昇雄20100628「東京新聞・文化」欄 御中
埼玉の読者です。
22日付貴紙5面の文化欄、内田雅敏氏の「花岡和解から西松へ」を読み反論します。記事の真ん中に笑顔の耿諄さんが載っているのは何故ですか? 貴紙はこの後、耿諄さんや孫力さんなどが弁護団に「騙された!」と、和解を拒否し抗議している事実を知らないのですか。この報道を耿諄さんが見たら「激怒」するでしょう。
弁護団は原告らに「共同発表」(90.7.5)の趣旨に則り和解と説明しましたが、当時、その判決文とも言える「和解条項」を原稿に提示しなかったのです。
しかも、その和解条項には共同声明に無かった「ただし、被控訴人は、右『共同発表』は被控訴人の法的責任を認める趣旨のものではない旨主張し、控訴人らはこれを了解した」と追記されていたのです。
当時、弁護団はこの「和解条項」を原告に提示しないどころか、和解の口頭説明の場でもこの「追記」部分を通訳しなかったことを『世界』(09.9 月号)の検証チームも認め(映像記録から)ています。しかし、「故意との指摘は当たらない」と結論付けましたが、故意でないなら何故か?『世界』などの反論の中で内田氏がこの部分に一切触れていないのは何故でしょうか。
後日、耿諄さんたちは口頭説明と和解条項が違うことを知り怒ったのです。当時、原告もマスコミもこの「和解条項」の内容を知らず、「原告以外にも補償が広がった」との弁護団の自画自賛の発表で世論は評価することになったのです。内田氏の言う「全員一致」での和解受け入れは、この様な状況の中で行われ。その時の笑顔が貴紙の写真です。
また、内田氏は「多くの人が和解を支持している」というが、原告にもならず思わぬ補償が出るなら名目は兎も角、合意する遺族も少なくでしょう。しかし、遺族ではない当事者の耿諄さんの思いや、ご遺族の孫力さんは「金ではなく尊厳だ!」と主張しているのです。また、記念館も「鹿島」に要求し、鹿島が建ててこそ意義があるのです。中国ハルピン郊外の方正で亡くなった4500人の開拓団犠牲者の「日本人公墓」を中国政府が建てたことは貴紙で既報の通りです。強制連行・労働等に対し日本政府が建てた墓地や祈念碑、謝罪碑が1箇所でもあるでしょうか。全て、当事者ではない自治体や市民やボランティアの建立です。
法的責任を認めないなら「賠償」でも「補償」でもなく、慰安婦基金と同じ支払い義務の無い「恵んでやる金」であり、鹿島には端金です。私は当事者ではなく和解の賛否に口を挟めませんが、正義や尊厳が「多数決」で決まるとは思わず、私は耿諄さんたちの思いを支持すします。
因みに平頂山裁判では敗訴しましたが「金ではなく尊厳だ!」と敗訴したにも関わらず弁護団は原告から感謝されているのは、この花岡の裁判と対照的です。
このような裁判を手弁当でやるのは当たり前であり、私は「住基ネット裁判」を最高裁まで闘い、弁護士は全てボランティアであった。しかし、判決文どころか準備書面など、その都度、全て私の手元に届いており、「和解条項」を原告に渡さず、肝心の部分を通訳もしないなど考えられない事です。
私は内田氏に手紙を出し、ご返事を戴きましたがこの件に何も答えず、ただ「裁判所も努力したか結果であり、理解して欲しい」としかありませんでした。彼は当時「和解条項」を提示しなかった理由、また、通訳しなかった理由を答えるべきです。
張宏波20100615関東日中平和友好会友好だより第45号「誰のための、何のための戦後「和解」なのか?」
2010年2月下句、北京で小規模ながらも意義深い会議が開催されました。暗礁に乗り上げている戦後補償運動の今後について意見交換をするため、日中双方で戦後補償問題に取り組んできた関係者20名以上が集まりました。
1990年代半ば以降、強制連行・強制労働、細菌戦被害、日本軍性暴力被害など多数の戦争遺留問題が日本の法廷で争われてきました。初期にはまともな審理に入ることなく結審されるといった状況もありましたが、日中双方の弁護士や支援者らのねばり強い努力の結果、被害の事実や企業・軍・政府の不法性が認定されるようになるなど、大きな成果をあげてきました。
ところが、2007年4月27日、強制連行・強制労働被害者が原告となった西松建設安野訴訟は、最高裁で原告敗訴となりました(以下、「4.27判決」)。前例主義を取る目本の法廷では、最高裁での判例はそれ以降の裁判の準拠となります。つまり、これ以降の裁判では被害者原告が勝訴する見込みが事実上なくなりました。これまで裁判を進めてきた弁護団は、裁判闘争の段階が実質的に終わってしまった以上、今後は政治解決を求めるしかない、と次の目標を掲げました。しかし、目立った進展は今のところありません。
こうした閉塞状況をどのように乗り越えていくのかを議論するための揚が、2月の北京会議でした。不思議なことに、これまで多数の訴訟か行われ、多くの支援者が関与してきましたが、関係者が一同に会する機会はほとんどありませんでした。
会議では、「4.27判決」の内容は法の正義に反し、日中共同声明を日本に都合良く解釈した一方的なものであり認められない、今後はこの間違った判決を覆す努力を重ねていかなければならない、という点から出発しました。また、同判決との関連で、中国人強制連行・強制労働問題が中心テーマとなりました。「これまで」と「これから」について活発な意見が交わされ、一度の会議では収拾が付かないほどでしたが、以下の一致点もありました。
それは、2000年11月に成立した花岡「和解」(花岡鉱山に連行された中国人被害者と鹿島建設との訴訟結果)は認められないという点でした。花岡「和解」は、被害者の意志を無視して日本側弁護団や支援者が主役となり、加害者に有利な「和解」を結んでしまい、被害者の一部はこの点について今も非難しているからです。しかも、昨年10月にはこの花岡和解を「モデル」として、西松建設と広島安野に強制連行された中国人被害者との間で「安野和解」が成立しており、花岡和解の「モデル化」が進むことへの危惧も共有されていました。
花岡「和解」にはどのような問題点があったのでしょうか?(詳細は、石田隆至・張宏波「東アジアの戦後和解は何に躓いてきたか?」『戦争責任研究』第66号、2009年12月)
被害者原告(11名)は鹿島建設に対し、「事実を認めて謝罪」「記念館の建設」「賠償金」の三点を要求しました。これに対し、成立した花岡「和解」では、「責任や謝罪が曖昧化」「記念館は事前に断念」「賠償金ではなく慰霊金」という内容で、原告の要求は一つも達成されでいません。「和解」成立後にこうした内実を知った原告と遺族のうち、原告団長の耿諄氏を含む原告3名のほか数名の遺族が、今も「和解」の受け入れを拒否しています。ところが、弁護団は言を弄して「鹿島は謝罪した」「あれは賠償金だ」と主張し続けています。代理人の役割とは、文字通り原告の主張・要求の代理にあります。代理人と原告とで解釈が食い違っている点だけをみても、代理人の越権は明らかです。
このような食い違いが生じたのは、代理人が事前に和解の内容をきちんと知らせなかったことが原因です。「和解条項」の最終案を事前に原告に渡すことさえなく、原告の要求は達成されたと口頭で伝えたのですから、原告らが後に「騙された」と言うのも当然のことです。誰のための、何のための「和解」だったのでしょうか。
今回、北京に集まった関係者らは、こうした花岡「和解」の問題点を今後繰り返させてはならないと確認しあいました。
ところが、去る4月26日、再び花岡モデルの「和解」が成立しました。西松建設が抱えていたもう一つの作業場である新潟信濃川に連行された中国人被害者との間の「和解」です。ここでも、実に不可解な「原告不在」が見られました。
今回の和解成立に先立つ3年程前、西松建設信濃川作業所で奴隷労働を強いられた被害者原告5名が起こした訴訟が、原告敗訴で終結しました。通常であればそれ以上の進展はないのですが、今になって「和解」が成立したのには、西松建設側の「事情」がありました。不正献金問題で企業体質を問われた西松建設が、人事の刷新とともに過去との決別を印象づけるため、強制連行問題という負の遺産の「解決」に乗り出したのです。
企業側にどんな意図があったにせよ、自ら和解を申し出るくらいですから、成立した「和解」には裁判の結果よりも前進している側面があるのではないかと期待されました。ところが事態は複雑で、この「和解」を受け入れた遺族がいた一方で、和解案の段階から受け入れられないと表明してきた被害者と遺族もいました。後者は、2007年まで西松建設を相手に最高裁まで訴訟を戦ってきた原告たちでした。彼らは、和解案の条件では受け入れられないと公的に事前表明していたにもかかわらず、西松建設と中国人被害者の代理弁護士らは「和解」を成立させてしまいました。この原告不在の「和解」成立に関して、中国側ではいくつか報道が続きましたが、日本では「時事通信」を除いて報じられることはありませんでした。
「和解」の受け入れを拒否した原告たちにとって、表面的な態度や言葉とは裏腹な西松建設の姿勢が容認できなかったのです。「4.27判決」では、企業による加害の事実が認定されていながら、日中共同声明を根拠にして被害者たちには請求権が行使できないとされました。「和解」交渉においても、西松建設はこの最高裁判決の結果を見直そうとはせず、むしろ出発点にしました。自分たちには法的責任がないから被害者に対する補償はしないという姿勢です。とはいえ、「歴史的な責任」という中身のはっきりしない責任を待ち出し、「償い金」を出すという結果になりました。
西松建設が信濃川作業所で強制労働をさせた被害者183名のうち、わずか半年たらずで12名が死亡した事実は、西松建設以外に責任主体はありえません。にもかかわらず、その責任を認めずに曖昧化し、金銭で解決するというのでは、まるで「慈善家」気取りと受け取られても仕方ありません。元原告らか拒否する心情も十分に理解できるものです。こうした側面がはっきりしていながら、一方の日本の弁護団が「和解」成立を強行したことは、どのような事情があれ、「被害者のための解決」とは逆方向になっていると言わざるをえません。
戦後の新中国が日本人戦犯に対して寛大な措置を行ったことは広く知られています。ただ、それは戦犯たちが被害者の立場や思いにまで深い思いを馳せるようになり、ありのままの事実と罪を認めて深く謝罪したという前提がありました。謝罪とは被害者に受け入れられる水準であってはじめて意味をなすものだということが分かります。
この経験と比較するとき、十年前の花岡「和解」、そして今回の西松建設との「和解」に何が欠如していたのかも見えてきます。急いで「和解」を結ぶ以前に、アジアの戦争被害者たちには今日も尊厳・人権が回復されていないこと、戦後日本社会はそうした被害者たちのことを直視しないで来てしまったこと、さらに、加害企業は中国人を使ったことで被害を被ったという理由で、戦後に政府から巨額の補償を受けていながら法的責任を負わないままでいる、等々の現実をもっともっと社会に発信して関心を高める努力をすぺきところでしょう。
中国と日本の間にある距離は今もなお決して小さいものではないようです。みなさんと一緒に内実ある「日中平和友好」のために努力していきたいと考えています。
戦時中、労働者不足で秋田の『花岡鉱山』(現「鹿島」)に強制連行され、虐待されながら強制労働を強いられた中国人労働者が一斉蜂起し脱出を図ったものの失敗した。花岡では強制連行された中国人の約半数の418名が犠牲になっている。その『花岡事件』で、現・「鹿島」との和解が成立した事は知られているが、その経緯と現状は殆ど知られていない。
この和解で原告は弁護団から『和解条項』を提示されておらず、更にその和解の口頭説明でも肝心の共同発表には無かった「追記部分」が通訳されていなかった。その後、弁護士の和解説明と「和解条項」が違うことを知った原告団長で当時、蜂起の隊長だった耿諄さんを含む原告3名の他、数名のご遺族が今も和解拒否していることも殆ど知られていない。
下記の「共同発表」と「和解条項」を比較して欲しい。
弁護団は「共同発表」を踏まえて和解、と原告に口頭説明したが、その「共同発表」には『鹿島建設株式会社は、これを事実として認め企業としても責任があると認識し、当該中国人生存者およびその遺族に対し深甚な謝罪の意を表明する。』と責任と謝罪が明記されていた。
しかし、その後の「和解条項」には『ただし、被公訴人は、右「共同発表」は被控訴人の法的責任を認める趣旨のものではない旨主張し、控訴人はこれを了解した。』と「共同発表」とはまったく逆に責任を否定している。
弁護団は何故か?この「和解条項」を原告らに渡さなかったのである。その批判に弁護団は「口頭で説明したと」主張するが、その口頭説明でもこの肝心な和解条項の「ただし書き」部分を通訳していなかったことを録画テープなどで確認されている。
以下、経緯を述べる。
この「議論」のキッカケは日本軍の「慰安婦」裁判でも証言している精神医学者の野田正彰氏の08年の雑誌『世界』の連載「虜囚の記憶を贈る」の指摘などから浮かんできた。(後に、『虜囚の記憶』みすず書房、に加筆のうえ収録)。
野田氏の『世界』掲載記事に田中宏氏や林伯耀氏などが、同誌に反論を書き議論になった。同編集部が「検証チーム」(有光健、内海愛子、高木喜孝、岡本厚の各氏)を組み検討した結果報告が『世界』09年9月号に出ている。
- 弁護団は「和解条項」を原告に提示せず、口頭で和解内容を説明した事を認めている。(『世界』08年7月号302P他、林伯耀氏)
- 更に、この口頭説明の時点で「共同発表」に無かった「右『共同発表』は被控訴人の法的責任を認めるものではない旨主張し、控訴人らはこれを了解した」との追記部分の、「特に『控訴人らはこれを了解した』との重要な一句は通訳されていなかったことが確認された」と認めている。(『世界』09年9月号289P、291P)
- しかし、結果として「弁護団が故意に説明を省略して原告らを『欺いた』との指摘は当たらないと判断する」と結論付けている。(同292P)
この検証結果は和解条項を提示しなかった「理由」が何処にも無く、また、今まで弁護団からの釈明もない。この様なゴタゴタにならないために「文書(和解条項)」が存在しているのであり、検証チームも「和解条項は判決書と同じ法的効力を持つ」(同284P)と認める程大事な「和解条項」を、弁護団はなぜ原告に渡さず通訳もしなかったのか?
私は「住基ネット」裁判を齊藤貴男氏らと共に最高裁まで闘い、弁護士はすべてボランティアだが、判決文のみならず準備書面などその都度、全て私の手元に届いている。弁護団が原告に「判決文(和解条項)」を渡さない事などあり得ず考えられないことである。また、「和解条項」を渡さなかった事と、その「肝心の部分」を通訳しなかった事は「偶然の一致」なのか?私は納得できない。弁護士はあくまで「原告代理人」であり、平頂山事件の裁判では「お金ではなく名誉と尊厳を守りたかった」と、敗訴しても弁護団は原告に感謝されている。(『平頂山事件とは何だったのか』高文研)
「花岡裁判」の弁護団長だった新美弁護士は既に亡く、私は過日、内田雅敏弁護士に手紙を出しご返事を戴いたが、私の「どうして和解条項を提示しなかったのか?」との質問に答えず、「裁判所もこれだけ努力した結果」とだけあり納得できない。
花岡和解で弁護団は責任を認め謝罪した「共同発表」を再確認と説明しながら、和解条項には「法的責任はない」と追記してあったのである。しかも、その「和解条項」を提示せず、口頭説明の場でも通訳されず原告に伝えられなかったのである。当時、原告は勿論マスコミもこの「和解条項」を知らず、「原告以外にも補償が広がった」との弁護団の自画自賛の説明を鵜呑みにして評価したのであり、これが『騙し』でなくて何であろうか!
これは鹿島が責任を否定した『謝罪無き和解』であり、「和解」とは事実を認め謝罪の上に成り立つものである。これは賠償金ではなく支払い義務の無い「アジア女性基金」と同じ「恵んでやる金」と言う事になる。花岡裁判の原告団長の耿諄さんや孫力さんたちも、「平頂山」裁判の原告同様「金だけではなく尊厳だ」との信念があると思い、私は耿諄さんたちの思いを支持する。
日本企業にとって金で済むなら安いものであろう、しかし、彼らが決して金だけではなく人間の『尊厳』を求めていることを、企業も日本政府も理解していない。
渡邊澄子20100507東京新聞「恐るべき人権無視 花岡事件」
「不再戦友好」の履行を
戦時下最大の言論弾圧事件といわれる横浜事件の被告とされた人たちの冤罪が認定されたのは何と今年二月のことだった。民主国家に生まれかわって六十五年を経たこの現実にはただ呆れる。だが戦時下に起きた事件で解決し切れていない問題はなお多い。記憶から消されてはならないひとつに「花岡事件」がある。
花岡事件は、秋田県花岡鉱山で一九四五年六月三十日深夜から七月一日未明にかけて起きた、拉致同様に強制連行された中国人労働者による蜂起である。中国人の強制連行は四三年四月の「試験的連行」に始まり、四四年八月から四五年五月にかけて計約四万人が日本全土百三十五事業所に配属されたが17.5%が死んでいる。鹿島花岡にダムエ事・河川改修に連行されたのは九百八十六人で、死亡率は42・5%と群を抜いている。死因が餓死、酷使死、私刑、拷問死だったことでいかに暴虐な事業所だったかがわかる。
終戦から四年後、朝鮮人の金一秀・李鐘応が姥沢(連行中国人の宿舎地)で散乱した無数の骨を発見し、留日華僑民主促進会に連絡。『華僑民報』(50年1月)の報道を受けて『アカハタ』が記事にした。秋田の鉱山作業員の長屋で生まれ育ち、プロレタリア作家として出発した松田解子はこのあと、裁判の証人として残留していた劉智渠ほかから体験を聞き、調査を重ねて代表作となる小説『地底の人々』(53年3月)を世に出した。
連行中国人たちは、ドングリ粉に果汁の絞り滓を混ぜた饅頭一個と皮付き蕗一本の一日二回の食事のために骨と皮の飢餓状態にあって、当初の十二時間労働は十六時間に強化された。飢えに耐えられず路傍の草を食べ、溝の水を啜って棍棒で殴り殺される日が続く。蜂起は殺され方の屈辱から中国人としての尊厳を守るための総意だった。だが彼らはたちまち警察官、警防団、憲兵隊、警備員、在郷軍人、青年団、一般住民らによる山狩りで全員が捕縛されてしまう。彼らは催事場の共楽館前広場に座らされ、炎天下で三昼夜、食も水も与えられず、日射病、顔の見分けもつかぬほどの殴打、共楽館内は針金での逆さ吊り、水責めほか拷問の舞台となって次々と殺された。首謀者とされた十二人に死刑(後に無期)のほか有期刑の判決は、知らされなかった日本敗戦後の九月十一日である。
一九四八年三月に、GHQによる軍事裁判で鹿島組関係者と警察関係者計六人に絞首刑を合む有罪判決がくだったが、やがて減刑。結局、全員が釈放され市役所職員になった人もいた。
第一次中国人俘虜殉難者遺骨送還船黒潮丸の出航は五三年七月で以後第九次まで続くが、六一年四月に結成された、松田解子を団長とする「遺骸新発見事件調査団」を中心に、中国人学生や朝鮮人団体、花岡の人たちによる一鍬運動で姥沢や鉢巻山の遺骨発掘運動が展開されたが今なお掘り尽くされてはいない。六六年五月には全国からの拠金によって「日中不再戦友好碑」が建立され、地元の人々によって毎年慰霊祭が行われている。
九死に一生を得られた人たちが犠牲者の鎮魂の意もこめて鹿島中国人強制連行損害賠償請求訴訟を提起したのは九五年三月、横浜事件で有効性を発揮したハーグ人権法の効果で鹿島が東京高裁の和解勧告に応じたのは二〇〇〇年十一月二十九日である。勧告による「基金の拠出」は「補償や賠償の性格」ではないという鹿島のコメントや、事前に和解条項を見ていないこと、歴史的罪業への謝罪のないことから決着と認めていない人が今もいる。
今年は天皇制国家のデッチ上げによる大逆事件、朝鮮半島を植民地支配した韓国併合条約締結から百年、花岡事件、原爆投下その他の果ての敗戦六十五年の節目の年である。まさに〈不再戦友好〉の誠実履行に向けて、私たちは真剣に考えなければならないだろう。
(わたなべ・すみこ=大東文化大名誉教授、近現代日本文学)

戦時中に新潟県内の信濃川でダム建設などの強制労働を強いられた中国人元労働者らが西松建設(東京)を訴え、最高裁判決で原告敗訴が確定した訴訟をめぐり、同社が約1億3千万円を信託して基金を設立し、金銭補償する条件で元労働者側と26日に和解することが、関係者への取材でわかった。和解条項には、元労働者側に対して「歴史的な責任」を認めた上での謝罪も盛り込まれる見込みだ。
訴訟は終結しているが、最高裁判決が「同社ら関係者が被害の救済に向けた努力をすることが期待される」と付言したことを踏まえ、双方で協議を続けてきた。26日に双方が東京簡裁に出頭し、「即決和解」する。
基金による補償は、新潟県内の信濃川で、発電所のダム建設などの強制労働を強いられた183人全員が対象となる。同社が約1億3千万円を信託して基金を設立し、中国の人権団体「人権発展基金会」に預託する。基金は、労働者や遺族の調査、慰霊碑の建立などにも使われるため、補償金額は1人当たり70万円以下になる可能性が高い。
同社は「歴史的な責任」を認め、「強制労働について歴史的な事実として認め、企業として元労働者や遺族に対し歴史的な責任があることを認めて深く反省し、謝罪する」という趣旨の謝罪を和解条項に盛り込む見通しだ。
同社を巡る戦時中の強制労働の問題では、昨年10月に広島県内の水力発電所の建設現場で働かされていたとされる360人に対し、2億5千万円の基金を設立して補償した例がある。今回は広島県に続く2例目。(柄谷雅紀)
石田隆至20100421いったい誰との、何のための「和解」なのか?
戦時中に中国人を強制連行・強制労働した西松建設が、信濃川作業所での被害者との間に和解を成立させる見通しだという報に接した(本紙4月17日付「強制労働和解 新潟も 西松建設 中国人側と26日」)。もちろん、西松建設がわずか半年ほどの間に連行者の約1割を死亡させた65年前の戦争犯罪について、率直に加害の事実を認めて謝罪し、賠償を行うということであれば歓迎すべきことだ。
しかし、3月23日付「時事通信」によれば、被害者のうち、長らく西松建設との訴訟を続けてきた元原告(訴訟自体は最高裁で原告敗訴が確定済)ら5名はこの和解案を拒否する声明を出しているという。和解案が明らかにされていない以上、元原告らが拒否した事情を推察するには限界がある。ただ、原告が拒否しているにもかかわらず、和解がまとめられようとしていることの異常さは看過すべきではない。西松建設はいったい誰と和解しようとしているのか?
被害者遺族の中にはこの5人の元原告らと異なり、和解案を受け入れる人たちもいることは分かる。しかし、裁判終了後にもかかわらず加害企業側が和解を申し入れたのは、そもそも元原告たちに対してではなかったのか? 当の原告らが拒否しているにもかかわらず、他の被害者遺族と和解するというのは奇怪という以外にない。しかも本紙記事では、基金は被害者の「183人全員が対象」とある。元原告らが和解案を拒否しようとも、被害者全員と和解が成立したことにするというのでは、原告不在ではないか?
日本で訴訟や交渉を行う中国人被害者には、日本人弁護士が代理人を務めているだろう。被害者の一番近くにいて苦労を共にした弁護士らは、和解の条件が整っていると考えているのだろうか。原告が拒否している和解案を成立させるというのは、弁護士倫理に反しないのか?
どのような内容であるにせよ、長らく訴訟を闘ってきた原告らが和解案を拒否しているということは、和解案が彼らの要求の許容範囲には到達していないことを意味する。にもかかわらずこのような和解を成立させてしまえば、尊厳の回復を求めて訴訟を起こした原告らは、再び日本側に人権を侵害されたと受けとめるであろう。戦後補償の実現どころか、さらなる「ねじれ」を生んでしまい、決して歴史「和解」に繋がるものとなりえない。アジアの被害者が受け入れられる解決を実現せずして「東アジア共同体」は不可能だ。
これくらいの条件なら「仕方がない」と日本側が判断しても、被害者側にとって受け入れられない水準でしかない。これは、日本が何度戦争への反省を表明してもアジア諸国からは「まだ不十分だ」とみなされることと裏表ではないか? このギャップを曖昧にすることなく正面から解消していくことが、被害者側の要求であると同時に、日本の国民的課題である。
以上
張宏波20100410何が日中間の溝を深めるのか?
4月2日付の野田正彰氏<今日の視角>「信濃川強制連行和解拒否」には、現在の日中間に刺さったトゲをどう抜くかに関する急所が指摘されていて、溜飲が下がる思いだった。
日中間の経済交流はもはや互いにとって不可欠なほど発展しているが、他方で政治的・社会的にはお世辞にも良好とはいえない。その遠因に戦争加害問題の未処理があるのはいうまでもない。もちろん、日本の良心的な知識人や市民運動家によって、戦後補償運動や被害者支援が地道に続けられてきており、在日中国人の一人として心から敬意を持っている。戦争被害に今も苦しむ中国人がいることも少しずつ知られるようになってきた。ただ、日本社会全体のうねりとして、かつての戦争がもたらした結果を直視し、歴史を清算して正常な対アジア関係の構築を願う動きが現れているとは言い難い。
なぜこのような残念な状況が続いているのかと日頃から感じていたなかで、野田氏の指摘は示唆的だった。日本側が提起した戦後補償問題の和解案を被害者たちが拒否したという。これは加害企業・西松建設の姿勢だけの問題ではない。和解案をまとめるのに被害者を代理した日本側弁護団もこれで妥協できると判断したはずである。戦後補償運動に携わるような良心的かつ献身的な日本人も、被害者が何を望んで日本政府や加害企業への訴えを起こしているのか十分理解できていなかったようである。
受けた被害そのもの、そしてそれ故に戦後も重ねてきた苦労は、どれだけお金を積まれても現状回復できない。誰よりもそのことを痛感している被害者がそれでもなお訴えたのはなぜか。事実とその責任を明確にし、そのうえで加害者が誠意ある謝罪をすることを求めていたからである。彼らの受けた想像を絶する苦難は、誰が何のためにこんなことをしたのかと問わずにはいられないのである。事実、ある強制連行被害者から「カネなんて要らない。どうして自分がこんなひどい目に遭ったのか知りたいだけだ」という声を聞いた。
野田氏は1月15日付コラムでも、花岡「和解」を題材に同様の指摘をしていた。これに対して弁護団の一人だった内田雅敏弁護士から反論(1月21日付)が寄せられていたが、人権派で知られる内田氏もまた、被害者の本当の声が聞こえていないのではないかと暗澹たる思いになった。花岡「和解」は500人が受け入れていて、数名しか拒否していないというが、数より主張の中身が大事ではないか。花岡「和解」を拒否する原告もまた、カネより正義を求めていたはずである。少数者の声に耳を傾けてこそ「人権派」ではないだろうか。それに、原告が「騙された」とまで主張する「和解」のあり方そのものの問題点を説明せず、なぜ「弁明」ばかりするのだろうか。
日中間の溝を深めるのは、被害者の声に向き合わず加害者の側の都合ばかり並べる不誠実な姿勢にこそある。何のための戦後補償運動だったのか、原点をもう一度確認すべき時にきているのではないか。(中国吉林省出身、大学教員)
内田雅敏20100121信濃毎日今日の視角「『花岡和解』から10年」への反論
寄稿 弁護士・内田雅敏
本紙1月15日付野田正影氏のコラム・今日の視角「『花岡和解』から10年」には、以下の3点において重大な事実「誤認」がある。
野田氏ば花岡和解には鹿島建設の謝罪がないと言う。しかし、和解条項1条は1990年7月5日の共同発表を再確認することから始まっている。共同発表は「中国人が花岡鉱山出張所の現場で受難したのは、閣議決定に基づく強制連行・強制労働に起因する歴史的事実であり、鹿島建設株式会社はこれを事実として認め、企業としてもその責任があると認識し、当該中国人及びその遺族に深甚な謝罪の意を表明する」としている。
野田氏は、和解は「日本の弁護士たちにだまされた」もので、日本と中国の関係者が全く正反対に評価したままであると言う。確かに中国人当事者たちの中に和解を非難する人はいる。しかし、和解はこの非難者を含む、花岡受難者聯誼会で十分議論した上で、全員の賛成によって成立した。遺族のI楊さんは、「今まで何度も会議をしてきたが、今日の会議が一番うれしい」と語った。この点については、「『花岡和舒を検証する』(「世界」2009年9月号、内海愛子ほか)でも検証されている。
現在、花岡受難者986人中、判明している生存者・遺族のほとんどである約500人が和解を支持し、和解金を受領し、また毎年6月30日、秋田県大館市主催の花岡現地での慰霊祭に順次来日している。和解評価をめぐって中国人すべてと日本人が対立しているかのような氏の論は事実に反する。
野田氏は、和解金は弁護士、支援者、被害者で3等分するとの伝聞を確認せずに記している。弁護士、支援者らは、和解成立までに費やした実質を含め、一切お金を受け取っていない。それは本件は中国人受難者の被害回復と同時に日本人自身の問題、つまり歴史の問題だからである。
野田氏のコラムがこのような重大な誤りを内包しているのは、<はじめに和解非難ありき>の基本姿勢の故である。氏はその主張に添う中国人にだけ耳を傾け、和解を支持している他の多くの中国人の存在をことさら無視している。このような姿勢は日中間の溝を深めるだけだ。
昨年10月23日、西松建設中国人強制連行・労働事件の和解が成立した。同社が加害の事実を認め、その歴史的責任を認識し、深甚な謝罪をするということを骨子とするもので、花岡和解の延長上でなされたものである。
和解成立後、受難者代表の邵義誠氏は「これまで闘ってきたが、今日からは、友人だ」と西松建設代理人と握手をした。翌24日、大館市の市民運動家たちによる花岡平和記念館の竣工式が行われた。草の根レベルの日中友好は確実に進行している。次は、信濃川河川敷で使役された中国人被害者と加害企業の和解が具現することを期待している。
(花岡事件、西松建設事件和解の中国人受難者側代理人弁護士)
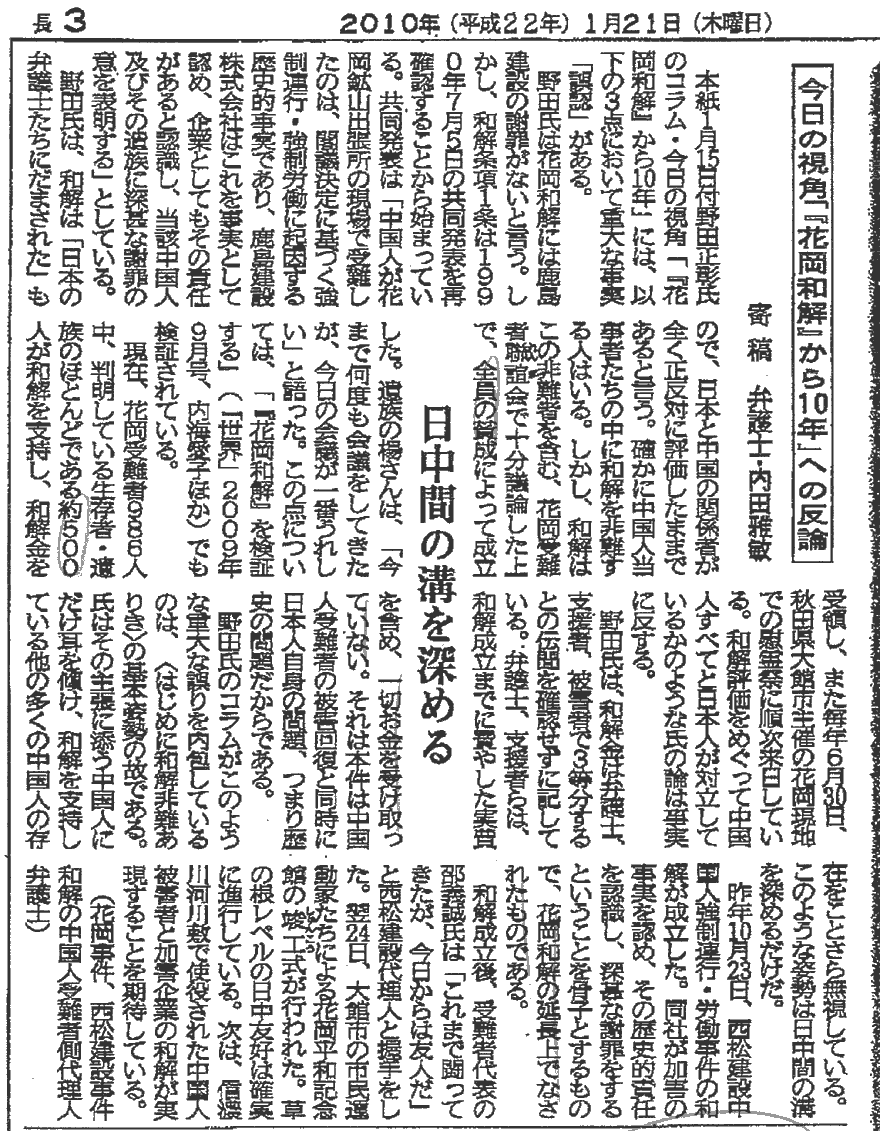
山邉悠喜子20100311『信濃毎日』新聞社に一言申し上げます
貴紙2010年1月21日、今日の視角「『花岡和解』から10年への反論」寄稿者は弁護士内田雅敏とあります。発言は寄稿者の随意でしょうが、以後何人かの方々がこれに反論したと聞いておりますがその後、反論の類が掲載されたようには見えません。特にテーマからしてこの問題には異論反論が予想されますが、新聞社は何故一般読者の反論を無視して一方の言い分だけ掲載されるのでしょうか? 掲載文は読者が自由に意見の交流出来る所だと考えていましたが、先ず御社の姿勢を問いたいと思います。
(一)
曖昧に被害者の願いを封じ込め、弁護団の主張だけを挙げることが果たして「日中間の溝を埋める」ことになるのでしょうか?
先ずこの文章の偽りについて2.3説明したいと思います。
1)1990年7月5日は、被害者は元より我々多少の支援を行った者にとって忘れられない一場面です。この時の『共同発表』には「当該中国人およびその遺族に深甚なる謝罪の意を表明する」とあります。鹿島の犯罪的事実は戦後横浜軍事法廷で計8人が起訴され、6人が有罪となって服役したことを見れば、国際法廷は加害企業事業所の犯罪性を認めたことになります。しかし「花岡和解」の冒頭第一条項は、「ただし、この『共同発表』は被控訴人(被告:鹿島)の法的責任を認める趣旨のものではない旨主張し、控訴人(被害者)らはこれを了承した」と続きます。共同発表の重要部分と、上記の戦後裁判をも否定しているのです。もし内田弁護士が掲げたように『共同発表』の通りに進行したのなら、問題にすることではありませんが、問題は続く大事な部分「……但し、」以降を述べていません。意図的ですか?
2)2段目には、「受難者連誼会で十分に議論した上で全員の賛成によって成立した」とあります。「和解勧告書」の提示があった2000,4,21を受けて同26日「考える会」の中心的人物と一部の原告が秘密に会議を開きました。この際原告団長の耿諄氏は重ねて『公開書簡』1989,12,21以後一貫して主張している三点の要求が守られるよう態度表明しました。原告が和解に同意して署名したのは(この主張を基礎にして)この時でした。でも実際には上述のように11,29『和解条項』と署名した04,21『和解勧告書』の内容は同一ではありません。
更に弁護団は、2000,11,18と19日、弁護士は敢えて説明の必要はないと思った(『専大社会科学研究所月報』09,9 p31)が原告側の強い要求によって、「和解」について説明するため北京を訪れ、18日中国紅十字会で、原告団長耿諄氏および中国側関係者(原告ではない)に説明しました。19日は、和解成立について関係者の祝辞が続き、原告の一人が異議を述べましたが、弁護士の「和解成功は目前、細かいことは以後に」と退けられた(孫力さん証言、および『尊厳』p363)とあります。では内田氏のいう「十分な議論」は何時何処でなされたでしょう? 今まで裁判に全く無縁のしかも農村に住む老人たちが、通訳を通じて口頭で一度説明されただけで内容を理解できるでしょうか? しかも、『世界』検証チーム(『世界』2009,9号)の記述では、その時に日、中両文書とも配布されず、口頭説明されたが通訳が『和解条項』第一項の「但し、…」以降の説明は通訳されなかったと書いています(同上p287)。
同じく『世界』(p288)には以上の確認が証明されているにもかかわらず「逐次日本語で説明していたことが確認される」と結論しています。そして「通訳が逐語訳されていない。 ……重要な一句は通訳されていなかったことも確認された」と書いています。ではどうしてこれが「十分議論」に値したといえるのでしょうか。
3)耿諄原告団長の、「騙された!! 日本の弁護士を信じた自分が愚かだった(2003,3,14耿諄氏発言:『平頂山日報』)」の述懐は深い信頼故の裏返しで、嘆息と共に出された発言です。決して野田氏の独自見解ではありません。
4)500人が和解を支持していると書かれていますが、反対している少数者も被害者の一人、又は遺族です。彼らの言葉は多数決に埋没してよいのでしょうか?
毎年大館市で現地慰霊祭が行われ被害者が順次来日していますが、和解に反対する少数者は全く招待されていないとのことです(孫力さん:私たちが南昌訪問時2009年8月に証言)。
そもそも「和解」に反対であることと虐待され異郷で命を落とした人々の遺族が肉親を想って慰霊することは、「和解」を進める日本側の意向で左右されて良いものでしょうか? 「花岡事案」そのものと、日本側の意向によるその後の和解とは違うものです。和解に反対する遺族は、慰霊の対象にはならないと判断されたら、加害事実によって引き起こされて悲惨な結果を生んだ「花岡事件」に対する認識を疑うことになります。
詳細は避けますが、「花岡和解」は、多くの問題を残しました。特に「花岡和解」成立より9年間一貫して日本弁護団の不当を訴え続けている原告がおり、弁護団はこれに対して一片の回答もしていません。これが「十分に議論した」結果だというのでしょうか? 少なくても原告の質問を無視し続けることこそが「日中の溝を深める」のではないですか。
私は直接関係者ではありませんから、原告が同意ならと考えていました。特に花岡裁判は戦後初めての訴えですから、支援組織をも含めて、参考にすべき点や教訓として反省し修正すべき箇所があるのは当然の事です。関わった方々が無批判に評価することの方が異常といえます。原告の意志をこそ代弁すべき弁護士が、あくまで自らの欠点を覆い隠していると見えます。原告の訴えに真面目に耳を傾け、その声を記事にした野田氏を非難攻撃されることは、現地で原告の訴えをつぶさに聞いた者としては納得致しかねます。同時に『信濃毎日』の報道機関としての良識をも疑います。
(二)
では何故今私たちが10年前のこの問題を問い直すのか?
1)「花岡和解」は、戦後損害賠償問題解決の第一歩、画期的和解とのマスコミ評価でしたが、その後も「花岡和解」が「花岡モデル」として定着し、以後の解決に一種の「基準」を作った事は否めません。西松和解については、「花岡和解」に比べて「謝罪」の字句が入った点、受取金額が多少増えたなどの進歩?の痕が見られるものの、決して被害者が求める真摯な謝罪や謝罪に見合った賠償ではない事です。
2)被害者の「仕方がない」の意味するものは?
戦後も半世紀が過ぎて、「日本には反人道的犯罪事実に対する反省もない(遅れた国)から、これ以上原則を求めても仕方がない」。あいも変わらぬ日本の歴史認識に対する批判と受け取れます。日本の弁護士が主導でやってくれたのだから、彼らも結果を出さなければ顔が立たないでしょう。(……だから仕方がない)。
3)まだ農村は貧しい。「少しでも金を手に出来れば被害者および遺族の安らぎになる」。反面、日本人の中に、「立派なことをいっても、結局中国人は金が欲しいんだ」。事実の反省より、僅かばかりの金を支払えば彼らは黙って従うだろう……。
農村の貧しさがあることは否定できません。が、「和解」「裁判」と被害者の貧しさは同一に論じることでは無いでしょう。
ある農民はいいました。「敗戦直後又は20年前ならまだしも、今あの加害者からありがたがってお恵みを頂かねばならないほど困窮しているわけではない」「困窮しても中国で乞食はしても、日本で乞食はしない」「農村の貧しさは中国自身が解決することだ」「裁判に関係ない」と被害者の何人かがはっきりと言い切ります。
4)敗戦後65周年を迎えます。直接の被害者は年々少なくなりましたから実体験のない遺族とは感覚が異なるのは当然です。実体験者が肉体的にも精神的にも受けた傷痕は今でも痛々しく聞く私たちの胸を刺します。過去に受けた屈辱に対する怒りが日本側作成の「和解条項」で完全に払拭出来るとは思えません。仕方がないと「和解」を受け入れた人も、心に深く刻まれた記憶を今は昔だと日・中の溝を埋められるでしょうか?
最早、戦後処理の問題は、個別裁判によって解決する時代ではないと考えます。真の解決は日本が自らの国家的犯罪に対する姿勢を問うしかないと痛切に感じています。勿論これらのことは、花岡裁判を皮切りに今まで15年間の貴重な経験から得られたものです。私は各位のこれまでの努力、本来の熱意を決して完全否定するものではないことを附記します。
報道機関が一方に与して報道の使命をないがしろにされることは私のような戦争体験者にとって過去の悪夢を彷彿とさせます。尊敬する『信濃毎日』が「日中の溝」の根源を十分に討議出来、日本社会の意識向上の場となることを期待しています。
(掲載に当たって、字句の間違いなどの指摘を受け小部分修正して掲載)
東京都八王子市 山邉 悠喜子 2010,3,11